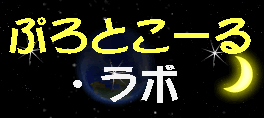日本選手団が練習で使っているテニスコートは、合宿所のすぐそばにあった。
大きなバッグをいくつも抱えて、冴子がコートにやって来た。すでに合宿所とテニスコートを何往復か行き来
している。毎日の練習では、男女レギュラー全員の荷物を彼女が一人でコートまで運ばなければならないの
だ。
している。毎日の練習では、男女レギュラー全員の荷物を彼女が一人でコートまで運ばなければならないの
だ。
これから練習だというのに、冴子が着ているのは館の制服だ。彼女の服装は、外出時は館の制服、合宿所内
は館で着ているテニスウェア、テニスコートでは体操服とブルマに限定されている。
は館で着ているテニスウェア、テニスコートでは体操服とブルマに限定されている。
「補欠の冴子がテニスウェアでコートに立つなんて、生意気よね」
合宿初日に、帆華がそう言いだしたのがきっかけだ。連盟理事長の一人娘である彼女の言うことには、選手
だけでなく、監督やコーチたちも逆らえない。その後、ミーティングで冴子の服装について規則が決められた
のだった。
だけでなく、監督やコーチたちも逆らえない。その後、ミーティングで冴子の服装について規則が決められた
のだった。
「おっぱいスケスケの館のウエアなら、いいんじゃないか?」
「スコート着用禁止にするとか」
「アンスコも禁止していいぜ!」
「ダメダメ、いくら館のいやらしいウエアでも、コートでウエアを着せるわけにはいかないわ」
男子が卑猥な提案をする度に、冴子の様子をチラチラ窺いながら、帆華が否定する。自分がいる前で侮辱的
な言葉を交わし、嬲るように笑い合いながら、彼女の服装規則を作っていく選手たちの様子に、冷静な冴子に
しては珍しく、頬が紅潮するほどの怒りと屈辱を覚えた。
な言葉を交わし、嬲るように笑い合いながら、彼女の服装規則を作っていく選手たちの様子に、冷静な冴子に
しては珍しく、頬が紅潮するほどの怒りと屈辱を覚えた。
「Good Morning!」
最後の荷物を運び終えた冴子に、恰幅の良いイギリス人男性が声をかけてきた。ボブというこの初老の男
は、仕事をリタイアして、ここのコートを管理しているオーナー管理人だ。冴子にはいろいろ親切にしてくれ
るのだが、どこか下心が透けて見えるようで、心を許すことができない。もちろん、表面上は礼節を持って対
応しており、今朝もにこやかに軽く会話を交わした。幼いころから国際的な選手を目指して育成されてきた冴
子は、英語が堪能だ。
は、仕事をリタイアして、ここのコートを管理しているオーナー管理人だ。冴子にはいろいろ親切にしてくれ
るのだが、どこか下心が透けて見えるようで、心を許すことができない。もちろん、表面上は礼節を持って対
応しており、今朝もにこやかに軽く会話を交わした。幼いころから国際的な選手を目指して育成されてきた冴
子は、英語が堪能だ。
レギュラーの荷物をクラブハウスに入れると、冴子はクラブの入り口に立った。そして、ボブがチラチラこ
ちらを見ているのを感じながら、制服のリボンを解いていく。
ちらを見ているのを感じながら、制服のリボンを解いていく。
ブレザーに続いて、ブラウス、スカート、そして下着と、冴子は着ているものをすべて脱いでいった。誰よ
りも早くコートに行き、クラブハウスの前で全裸になって、選手やスタッフのお出迎えをすること、これも選
手たちが定めた服装規則に書かれたことの一つだ。
りも早くコートに行き、クラブハウスの前で全裸になって、選手やスタッフのお出迎えをすること、これも選
手たちが定めた服装規則に書かれたことの一つだ。
何も身に付けていない裸体が、朝日の中で白く輝いている。素晴らしくスタイルが良いので、一瞬、彫刻か
と見まがうが、生身の人間であることはすぐにわかる。フェンスの向こうは一般道になっているため、時折、
通行人が驚いた表情で冴子を見ながら通って行った。なにしろ、東洋人の美少女が全裸でクラブハウスの前に
立っているのだ。
と見まがうが、生身の人間であることはすぐにわかる。フェンスの向こうは一般道になっているため、時折、
通行人が驚いた表情で冴子を見ながら通って行った。なにしろ、東洋人の美少女が全裸でクラブハウスの前に
立っているのだ。
三十分ほどして、ようやくレギュラーたちがやって来た。
「おはようございます!」
冴子が深々と頭を下げた。
「おはよう」
最初にやって来た飯森が冴子に声をかけ、その乳房を鷲掴みにした。飯森の手の中で、冴子の柔乳が淫らに
形を変える。
形を変える。
「うっ…」
力いっぱい揉まれて、冴子が痛みで呻き声を漏らした。飯森がニヤニヤ笑いながら、ハウスの中に入ってい
く。
く。
「おはようございます!」
「おはよう」
こうして男女を問わず、選手、スタッフの全員が朝の挨拶がわりに冴子の素肌に触ってくる。
「冴子の身体って、ホント綺麗よね」
うっとりした表情を浮かべながら、胸から下腹部まで、筋肉の動きを確かめるかのように丹念に撫で摩るの
は帆華だ。女子のキャプテン彼女は、お気に入りの人形かペットのように、冴子のことを偏愛しているのだ。
は帆華だ。女子のキャプテン彼女は、お気に入りの人形かペットのように、冴子のことを偏愛しているのだ。
他の選手と雑談を交わしながらやって来た須崎雅裕の手が、冴子の股間に伸びる。いきなり陰部を弄られた
冴子は、反射的に腰を引いてしまう。
冴子は、反射的に腰を引いてしまう。
「おい、ちゃんと触らせろよ!」
「すみません…」
須崎に触らせるために冴子が腰を突き出すと、卑猥な笑い声をあげた須崎の掌が大陰唇を鷲掴みにし、指が
膣内に入ってくる。彼と一緒に来た部員が背後に回って彼女の双乳を揉みしだいた。
膣内に入ってくる。彼と一緒に来た部員が背後に回って彼女の双乳を揉みしだいた。
「うっ…あ、うう…」
乳首を掌で転がすように擦られて、冴子は思わず声を漏らしてしまう男の手の中で乳頭が尖り始めた。一方
の須崎は、冴子の秘孔に指を二本挿し込んで掻き回した。指を曲げ、秘孔の天井を擦る。
の須崎は、冴子の秘孔に指を二本挿し込んで掻き回した。指を曲げ、秘孔の天井を擦る。
「あっ、ああ…、あ、ああぁ…」
冴子が腰を揺すり、喘ぎ声を漏らした。背中がピンッと伸び、全身がピクピクッと痙攣し、軽いアクメを迎
える。
える。
全員がクラブハウスに入ると、冴子は全裸のままコートに向かう。
管理人のボブの前を通る時に会釈すると、厚い大きな手が冴子のお尻を撫でた。
「You're so cute!」
ニヤッと笑ったボブの表情は、日頃の紳士ぶりとはかなり違ったものであった。その変化が冴子の心に突き
刺さる。異邦人の彼の目から見ても、自分は卑猥な玩具になり果てているらしい。
刺さる。異邦人の彼の目から見ても、自分は卑猥な玩具になり果てているらしい。
コートに入ると、スタッフが好奇の視線を冴子に向けてくる。日本から来たスタッフは、彼女が置かれてい
る境遇を熟知しているが、現地スタッフの中にはたまたまやって来た者もおり、全裸でいる少女に驚いた表情
を見せ、こちらを指さして何かしきりに言い合っている。
る境遇を熟知しているが、現地スタッフの中にはたまたまやって来た者もおり、全裸でいる少女に驚いた表情
を見せ、こちらを指さして何かしきりに言い合っている。
"邪魔だよ、このアバズレ!"
よく太った仏頂面の中年女のスタッフが、コート整備のブラシの柄で冴子のお尻を突いた。
"どこでも裸になりたがる変態なんだって、若い娘が信じられないよ、姦淫の罪で地獄に落ちるわよ、まった
く!"
く!"
英語でそうまくしたてながら、女が冴子を追い立てると、周囲で笑い声が起きた。屈辱のあまり、冴子が唇
を噛みしめる。
を噛みしめる。
そうこうしているうちに、テニスウエアに着替えたレギュラー選手たちがコートにやって来た。
「さあ、着替えなさい」
冴子に近づいてきたのは女子選手の一人、吉池香澄だった。日替わりでレギュラー選手の中から冴子の指導
当番が決められており、その当番からブルマと体操着が渡されると、ようやく服を着ることが許される。
当番が決められており、その当番からブルマと体操着が渡されると、ようやく服を着ることが許される。
香澄は、体操服とブルマを指先で摘み、冴子に投げるようにして渡した。
「穿く前に、ブルマをよく確認するのよ」
意地悪そうな笑みを浮かべて香澄が言う。冴子がブルマを広げると、股間の部分に白い粘液が付着してい
る。
る。
冴子が見つめると、香澄は嘲笑するような表情を浮かべた。高校在学とともにプロ登録し、それなりにテニ
スの実力はあるものの、本来であれば国際試合に出られるレベルの選手ではない。それが「ジュニア・トーナ
メント・テニス」の選手に選ばれたのは、ひとえに帆華と親しかったからだ。自身それがわかっているだけ
に、ここに来て、帆華が冴子にばかり構うのが面白くない。
スの実力はあるものの、本来であれば国際試合に出られるレベルの選手ではない。それが「ジュニア・トーナ
メント・テニス」の選手に選ばれたのは、ひとえに帆華と親しかったからだ。自身それがわかっているだけ
に、ここに来て、帆華が冴子にばかり構うのが面白くない。
「冴子が素っ裸で待っていて可哀そうだから、温めてあげてって、須崎君に頼んだんだけどね」
「チ×ポで体操服やブルマを擦って、ちゃんと温めてやってたじゃないか」
須崎がニヤニヤ笑いながら近づいてきた。見ると、体操服の方もあちこちに、先走り汁が付着したらしい染
みができている。
みができている。
「かえって、濡れて冷たくなってるじゃないの」
「ブルマは、特に気合入れたからな…」
須崎がとぼけた調子で言った。明らかに二人で示し合わせて、冴子が身に着ける物を汚したのだ。
「なあ、冴子、うれしいよな」
須崎が目に力を込めてそう言った。お礼を言って、喜んで着ろという意味だ。
「ありがとうございます」
できるだけ感情を見せない、覚めた声でそう言うと、冴子はべっとりと精液が付着した部分をしっかり股間
に密着させて履いて見せた。冷たくヌルヌルした感触が性器に触れるのが気持ち悪く、全身に鳥肌が立つ。
に密着させて履いて見せた。冷たくヌルヌルした感触が性器に触れるのが気持ち悪く、全身に鳥肌が立つ。
「温かくて最高の履き心地です、ありがとうございます」
あえてブルマの股間をしっかり食い込ませ、冴子がお礼を言うと、香澄と須崎が声をあげて笑い出した。
そして、練習が始まった。しかし、冴子がラケットを持つことはない。冴子の練習時間のほとんどが、球拾
いやコートの整備に費やされる。
いやコートの整備に費やされる。
「冴子―っ!」
須崎が冴子をコートに呼んだ。
「そこで、四つん這いになれ」
冴子がコートで四つん這いになると、彼女の身体を的にして、男子選手たちが順番にサーブを打ち始めた。
「うっ…」
男子が力いっぱい打った硬くて黄色いボールが、彼女の背中に命中する。背中をのけ反らせて、冴子が呻き
声を漏らす。
声を漏らす。
「あっ…、うっ!ううっ!」
脇腹に、お尻に、背中に…、強い打球を次々に身体に受けて、冴子が声を漏らす。
「もう少し、シビアなコントロールを練習したいな…」
「よし、冴子、そこで座って脚を開け!」
男子の指示を受けて、冴子はブルマを脱ぐと、コートの真ん中で両手を頭の後ろに組み、M字開脚の姿勢に
なった。白い太腿の間につるつるにそり上げられた下腹部、その中心に口を開き、ピンク色の肉びらをのぞか
せた大陰唇の膨らみが露わになる。
なった。白い太腿の間につるつるにそり上げられた下腹部、その中心に口を開き、ピンク色の肉びらをのぞか
せた大陰唇の膨らみが露わになる。
「よし、始めるぞ!」
須崎の合図で、男子選手たちがサーブ練習を再開した。
立て続けに打ったサーブが、剥き出しの足や太腿に当たる。ボールが当たるたびに、冴子は歯を食いしばっ
て、痛みを堪えた。
て、痛みを堪えた。
「惜しいなぁ…」
須崎が悔しそうに手を振る。男子たちは冴子の性器を的にボールを打ち込もうとしているらしい。
男子の最後に飯森がサーブの構えをとった。男子選手で最も実力がある彼は、軽くトスを上げて、思い切り
ラケットを振りぬく。
ラケットを振りぬく。
「くうっ!」
飯森の打ったボールが女陰の上部、ちょうどクリトリスのあたりに命中した。突き上げるような痛みに、冴
子は呻き声を漏らし、蹲るようにして身体を丸めた。男たちの笑い声が頭の上から降ってきて、固く閉じた目
尻に涙が滲んだ。
子は呻き声を漏らし、蹲るようにして身体を丸めた。男たちの笑い声が頭の上から降ってきて、固く閉じた目
尻に涙が滲んだ。
夜、夕食、ミーティング…と、正規のスケジュールが終わった後、選手たちに命令された私用、雑用をこな
した冴子が時計を見ると、すでに夜10時を回っていた。
した冴子が時計を見ると、すでに夜10時を回っていた。
毎晩、選手やスタッフの部屋を回って性欲を処理するのが、彼女の夜の仕事だが、今夜はリビングに来るよ
う、須崎から指示されていた。
う、須崎から指示されていた。
「なんだ、遅かったじゃないか」
リビングには男子選手が集まっており、その中心にいる須崎がそう言った。
「申し訳ありません」
そう言うと冴子は深々と頭を下げた。こちらに来てからいつも感じていることだが、謝罪する時に、こうし
て相手に顔を見せずに済むのは、冴子にとっては好都合だった。彼女の顔は今、おそらく怒りで強張っている
だろう。声だけなら、クールな口調を装い続けることが冴子には可能だ。
て相手に顔を見せずに済むのは、冴子にとっては好都合だった。彼女の顔は今、おそらく怒りで強張っている
だろう。声だけなら、クールな口調を装い続けることが冴子には可能だ。
「注文していた雑誌が日本から届いたから、冴子と一緒に読みたいと思ってね」
そう言うと、須崎はテーブルの上に数冊の雑誌を並べていく。冴子の表情がピクリと動いた。
『星の園』と書かれたその雑誌は、国防省付属慰安施設・星園癒しの館が毎週発行している機関誌だ。一般
の書店には出回らず、館内で販売されている以外は、国防省や防衛隊内を中心に出回っている。とりわけ、海
外派兵されている部隊には、オナネタとして必需品だと言われていた。
の書店には出回らず、館内で販売されている以外は、国防省や防衛隊内を中心に出回っている。とりわけ、海
外派兵されている部隊には、オナネタとして必需品だと言われていた。
一見すると、グラビア雑誌のようだ。表紙には毎号、目を見張る程の魅力的な美少女が掲載される。もちろ
ん、全て館に所属する慰安嬢だ。机に並べられたものは、有岡美奈、井上千春、中西朋美など全てテニス部員
が表紙を飾っており、少し前に撮影した冴子自身が表紙になったものもあった。
ん、全て館に所属する慰安嬢だ。机に並べられたものは、有岡美奈、井上千春、中西朋美など全てテニス部員
が表紙を飾っており、少し前に撮影した冴子自身が表紙になったものもあった。
「これ、スゴイよな…」
言いながら、須崎がページをめくる。全編、慰安嬢たちの裸体やセックスしている写真がふんだんに使わ
れ、市販のアダルト雑誌では足元にも及ばさない程の卑猥な内容になっている。巻末には慰安嬢名鑑がついて
いて、見ているだけでも妄想が膨らむが、館を訪問してサービスを受ける時には実用的な指名用のカタログに
なる。戦地に派遣された防衛隊員たちの中には、戦功によって与えられる帰還後の無料滞在を励みに、自らの
生命の危険をかける者もいるという。
れ、市販のアダルト雑誌では足元にも及ばさない程の卑猥な内容になっている。巻末には慰安嬢名鑑がついて
いて、見ているだけでも妄想が膨らむが、館を訪問してサービスを受ける時には実用的な指名用のカタログに
なる。戦地に派遣された防衛隊員たちの中には、戦功によって与えられる帰還後の無料滞在を励みに、自らの
生命の危険をかける者もいるという。
「飯森へのおススメはやっぱり、これだよな!」
須崎が飯森に渡したのは、凛として美しいテニスウエア姿の美奈が表紙になっている一冊だった。
「えっ、ああ、それな…」
飯森が照れくさそうに頭をかいた。実は、彼は美奈の大ファンだった。プロを目指すテニスプレイヤー同士
なので「ファン」というのも妙なのだが、テニスのセンスや技量を評価しているとか、アスリートとして尊敬
しているということはもちろん、それにとどまらず、言わば「アイドル」としての美奈を愛し、イメージ動画
を見たり、写真集まで買う程の、文字どおりのファンである。
なので「ファン」というのも妙なのだが、テニスのセンスや技量を評価しているとか、アスリートとして尊敬
しているということはもちろん、それにとどまらず、言わば「アイドル」としての美奈を愛し、イメージ動画
を見たり、写真集まで買う程の、文字どおりのファンである。
「でも、美奈ちゃんはすっかり慰安嬢に染まったようだね…」
複雑そうな表情を浮かべて、飯森が開いたページには「有岡美奈のすべて!」と言う見出しで、ユニホーム
姿で立つ美奈の姿が載っていた。よく見ると、その顔や口、胸、下腹部、太腿…と、それぞれ注釈がついてい
る。
姿で立つ美奈の姿が載っていた。よく見ると、その顔や口、胸、下腹部、太腿…と、それぞれ注釈がついてい
る。
《慰安譲3年有岡美奈です。癒しの館に私たちのテニスを見に来てください。
この口で数えきれないぐらいの本数のオチンチンをしゃぶりました。精液も一滴も零さず飲めます。
自慢のオッパイです。乳首もクッキリ、もちろんお触りだってOKです。揉み心地抜群ですよ。
オマンコも鍛えています。締りも濡れ具合も抜群だって評判です、ぜひ館に来て、あなたのオチンチンで試
してみてください。
してみてください。
太腿にお尻、割れ目だって、いつもあなたに見てもらえるようにしています。写真撮影も大歓迎です。》
須崎が一つ一つ、指差しながら、声をあげて読み上げていく。その度に、男たちの卑猥な合いの手や嘲笑が
起きる。
起きる。
ページをめくると、同じポーズで全裸の美奈が載っている。
《気合を入れるため、陰毛は剃っています。ツルツルの恥丘と割れ目は私たち星園テニス部員の証です。慰安
譲になれたことを誇りに思います。》
譲になれたことを誇りに思います。》
そこから数ページにわたって、二人の男を相手に3Pでセックスする美奈の姿が続いていく。無修正の陰部
から精液が溢れ出す写真には、「金バッチのみなさんであれば、膣内射精もお受けいたします」と書かれ、前
後の穴に2本刺しの写真には「アナルも使用可能です。実はこちらのほうが感じてしまいます、アナルも遠慮
せずお使いください」と書かれていた。
から精液が溢れ出す写真には、「金バッチのみなさんであれば、膣内射精もお受けいたします」と書かれ、前
後の穴に2本刺しの写真には「アナルも使用可能です。実はこちらのほうが感じてしまいます、アナルも遠慮
せずお使いください」と書かれていた。
「これが今の有岡美奈かよ」
飯森が侮蔑を込めて笑った。その声のトーンは失望というよりも、もっと隠微な響きを含んでいる。
「テニス界のプリンセスも、すっかり汚れたもんだよなぁ…」
須崎の声に、男たちが一斉に笑い声をあげる。冴子はこみ上げる怒りを必死で抑えていた。
男子選手の一人が、全裸の冴子が男と背面座位で、結合部を剥き出しにして繋がっている写真を見つけ、ニ
ヤニヤ笑いながら指先で示した。しかし、冴子の心をギュッと締め付けたのは、むしろ、その横で男に犯され
ている鳥居仁美の姿だった。可愛い妹分であり、心から信頼する「相方」でもあった生真面目な少女は、上下
の口に男の肉棒を挿入され、今にも泣きそうな表情を浮かべている。
ヤニヤ笑いながら指先で示した。しかし、冴子の心をギュッと締め付けたのは、むしろ、その横で男に犯され
ている鳥居仁美の姿だった。可愛い妹分であり、心から信頼する「相方」でもあった生真面目な少女は、上下
の口に男の肉棒を挿入され、今にも泣きそうな表情を浮かべている。
「なあ、冴子、ここで慰安嬢のテクニックを見せてくれよ」
「いいね、それ!」
「飯森、メス豚美奈に裏切られた思いを冴子にぶつけてやれ!」
男たちが口々に囃したてる中、飯森が下半身裸になってソファに腰かけた。冴子はパンティを脱ぎ、ソファ
に上がって飯森の腰を跨ぐ。
に上がって飯森の腰を跨ぐ。
「冴子、解説しながら、やってくれよ!」
須崎の声が飛び、他の選手たちが大喜びで拍手した。一瞬、冴子の醒めた視線が羽目を外しつつある男たち
を見渡す。
を見渡す。
「オ××コに、オ×ン×ンを入れます…」
冴子は怒張を右手で掴んで、亀頭を膣口にあてがう。
「先っぽを入れたら、一旦、膣口で亀頭を扱きます…」
「うっ…、あぁぁ…」
飯森が思わず声を漏らした。亀頭を飲み込んだあたりで止め、入り口で擦るように出し入れする。
「締まって、気持ちいい所ですよね…、カリのあたりが引っかかって…」
「続いて、奥まで入れます…」
そう言うと、冴子は改めて腰を持ち上げて態勢を整え、怒張に手を当てる。
「あぁ…、入ります…」
肉棒が根元まで挿入される。他の男たちはニヤニヤ笑いながら、結合部分を鑑賞した。
「オ××コで、オ×ン×ンを根元まで掴んでるのがわかるでしょう…」
快感のあまり、もはや苦痛を堪えているような表情をした、飯森が声も立てられない様子でウンウンと首を
縦に振る。
縦に振る。
「キ×タ×、触りますね、失礼します…」
そう言うと、冴子は肉棒を挿入したままの状態で、飯森の睾丸を両手で撫であげ、マッサージし始めた。
「慰安嬢はセックスの時、ホントに感じてるんだって?」
「はい…、『感じた演技』は許されないので、身体が敏感になるよう開発されます…」
そう言うと、冴子は、再び肉棒を根元まで全部呑み込み、ゆっくりと出し入れした。ヌルっと濃い蜜がサオ
に絡みつきキラキラ光る。本気で感じている証拠を見せたのだ。
に絡みつきキラキラ光る。本気で感じている証拠を見せたのだ。
「オ×ン×ンを入れただけで、こんなにヌルヌルになってしまいます…」
「ホントだ、すげぇ、グショグショだぜ!」
男たちが一斉に結合部を覗き込むと、須崎が手を伸ばして弄りながら、嬲るように大声で囃した。
「オ××コの締まりも凄いんだって?」
「飯森、わかるか?」
「ううっ、どうかな…、すごく気持ちいいのは間違いないけど…」
もはや射精をこらえるのが精一杯で、飯森にはまったく余裕がない。
「冴子、わかるようにしてやれよ!」
須崎がそう言うや否や、飯森が身体をのけ反らせた。
「うっ!ううっ…、スゴイ、スゴイよ、コレ!」
「どうしたんだ?」
「根元、真ん中、亀頭と順番に締まっていくんだ…」
「慰安嬢は毎日膣の鍛錬を行うことで、膣圧の向上と締め付け方のバリエーションを身につけます…。私は膣
の入り口、真ん中、奥の部分をそれぞれに締めつけることができます」
の入り口、真ん中、奥の部分をそれぞれに締めつけることができます」
「『星の園』には、冴子は今年の慰安嬢名器十選に選ばれたと書いてあるな。これ、どういうことか説明して
くれよ」
くれよ」
「癒しの館では性交実習の授業がありますが、年一回、常連客の皆様によるオ××コの品評会があります。今
年は『三段締めに加えて、膣壁のヒダヒダのチ×ポへの絡みつきが気持ち良く、素晴らしい』と評価されまし
た…」
年は『三段締めに加えて、膣壁のヒダヒダのチ×ポへの絡みつきが気持ち良く、素晴らしい』と評価されまし
た…」
「うう…、もうダメだ、我慢できない…」
寸止めの連続で我慢できなくなった飯森が、フィニッシュを要求した。
ゆっくりと2、3擦りした後、残像が残るくらいのスピードで腰を上下に動かす、しかしお尻はぎりぎり接
する程度、尻の弾力が刺激になるくらいで相手に負担はかけない足腰のバネを使いで、激しく肉棒を扱き上げ
る。
する程度、尻の弾力が刺激になるくらいで相手に負担はかけない足腰のバネを使いで、激しく肉棒を扱き上げ
る。
「はぁ…、これが、はあぁ…、私の得意技の『フラッシュ・チ×ポ擦り』です…」
喘ぎ声をあげながら、冴子が説明した。単にセックスするのではなく、何かの技を開発し、審査員にそれを
命名してもらうことが義務付けられていた。
命名してもらうことが義務付けられていた。
「うっ、出る…、気持ちいい…、出るっ!」
あっという間に飯森が呻き声をともに、冴子の中に射精した。
「あ…、あっ…、ああぁ…」
冴子が同時に達して、最後はサオから亀頭全体をギュと締め付け、精液を搾り取った。そして、肉棒を抜き
取ると、そのまま口にくわえ、お掃除フェラをする。
取ると、そのまま口にくわえ、お掃除フェラをする。
「俺も、悶絶テク、経験したい!」
「俺も!」
男たちがこぞって手をあげ、順番に冴子のテクニックを試す。最後の須崎が射精すると、ワイングラスを取
り出して冴子に渡して目くばせした。おそらく、さっき『星の園』で記事を見つけたのだろう。
り出して冴子に渡して目くばせした。おそらく、さっき『星の園』で記事を見つけたのだろう。
冴子は股間にグラスを持っていった。膣に力を入れると、白濁したザーメンがトロリとグラスに注がれる。
それを口にあてると、冴子は最後の一滴まで飲み干し、ワイングラスの底まで舐める。
「すっげぇ、イヤらしいなぁ…」
「今度は、アナルセックスの実力を見たいなぁ…」
「そうだな…」
その時、室内電話が鳴った。須崎が取ると、受話器の向こうから、焦れたような帆華の声が聞こえた。
「さあ、もう男子はいいでしょ?今夜は、私が冴子と一緒に寝るんだから…」
ベッドの横たわった冴子は、豊かな膨らみを見せる帆華の乳房を大きくゆっくり揉みしだいた。
「…あ、ああン、冴子…」
彫の深い顔を赤く染め、帆華が甘えた声を漏らす。秘部が疼くのか腰を振り、むっちりした太腿で冴子の太
腿を挟み込んだ。
腿を挟み込んだ。
「可愛いわよ、帆華…」
冴子が唇を寄せると、待ち構えたように帆華が唇を重ねる。口を吸い合いながら、帆華は疼く股間をグリグ
リと冴子の太腿に擦りつけた。そして、甘く鼻を鳴らし、舌をヌラヌラと舌に絡めてくる。
リと冴子の太腿に擦りつけた。そして、甘く鼻を鳴らし、舌をヌラヌラと舌に絡めてくる。
男性からはちやほやされ、同性からは好かれない帆華だが、やっかいなことに、本人は男性よりも女性に性
的魅力を感じるレズビアンだった。とりわけ、クールでキリッとした硬質の美女が好みのタイプで、冴子はま
さに理想の相手である。冴子に対する意地悪は、好きだという気持ちの不器用な表現に過ぎない。
的魅力を感じるレズビアンだった。とりわけ、クールでキリッとした硬質の美女が好みのタイプで、冴子はま
さに理想の相手である。冴子に対する意地悪は、好きだという気持ちの不器用な表現に過ぎない。
そのことに気づいた冴子は、むしろ、積極的に身体を開き、冴子の欲望を受け入れることにした。全日本テ
ニス連盟理事長赤坂良徳の一人娘というカードは、持っていて損はない。おかげで、最近ではバイブを仕込ん
だ「逃走防止」の貞操帯も免れるようになっている。
ニス連盟理事長赤坂良徳の一人娘というカードは、持っていて損はない。おかげで、最近ではバイブを仕込ん
だ「逃走防止」の貞操帯も免れるようになっている。
唾液をいやらしく引き合うほどの熱いディープキスを交わしたあと、冴子の舌が耳から首筋を舐めていく。
「あ…、あぁ…、あぁぁ…」
帆華がクネクネと腰を振り、全身で快感を表した。二人の間では、冴子がタチで帆華がネコになる。冴子の
指が、帆華の身体をねちっこく這い回った。掃くように、あるいは転がすように、巧みな指使いで乳房や乳首
を愛撫して、帆華の官能を蕩かせていく。帆華の方も、負けじと冴子の乳房を揉んだり、首筋を舐めたりする
が、到底、冴子には及ばない。
指が、帆華の身体をねちっこく這い回った。掃くように、あるいは転がすように、巧みな指使いで乳房や乳首
を愛撫して、帆華の官能を蕩かせていく。帆華の方も、負けじと冴子の乳房を揉んだり、首筋を舐めたりする
が、到底、冴子には及ばない。
「ああ…、気持ちいいわ…」
吐息交じりの声を帆華の耳に吹き込むように、冴子が囁いた。そうすることで、相手の興奮がさらに高まっ
ていく。そして、彼女自身の身体も、同時に高めていかなければならない。冴子は片手で自らの女陰を弄った
後、その手を帆華の下腹部に滑り込ませる。二本の指が花唇を卑猥に盛り上がらせながら、いやらしく周囲を
なぞる。間に挟まれた秘唇は、真っ赤に充血して愛益を溢れさせていた。
ていく。そして、彼女自身の身体も、同時に高めていかなければならない。冴子は片手で自らの女陰を弄った
後、その手を帆華の下腹部に滑り込ませる。二本の指が花唇を卑猥に盛り上がらせながら、いやらしく周囲を
なぞる。間に挟まれた秘唇は、真っ赤に充血して愛益を溢れさせていた。
「ああ…、冴子、好きよ…、好きよぉ…」
女体の中心にある敏感な部分を弄られて、帆華がうわ言のように呟く。冴子の指が帆華の膣に挿入された。
ヌチャヌチャと抜き差しを開始しながら、「可愛いわよ」と冴子がほほ笑んだ。
ヌチャヌチャと抜き差しを開始しながら、「可愛いわよ」と冴子がほほ笑んだ。
ゆっくり時間をかけてお互いの身体を愛撫し合った後は、いよいよフィニッシュだ。
「はあっ、はあっ、はあ……」
どちらのものとも付かない荒い吐息が、部屋の中を満たしている。二人はシックスナインの態勢になって、
お互いの性器を舐め合った。ペチャペチャという淫らな音が、室内に響く。
お互いの性器を舐め合った。ペチャペチャという淫らな音が、室内に響く。
いつもやられてばかりで悔しいからと、今日は帆華が上になっていた。帆華の秘孔から愛益がポタポタと溢
れ出落ちて、冴子の口の周りを濡らす。柔らかい唇が、淫蜜に濡れテカテカと輝いている。
れ出落ちて、冴子の口の周りを濡らす。柔らかい唇が、淫蜜に濡れテカテカと輝いている。
冴子は帆華の女陰にむしゃぶりついた。
「いいっ、いい…、変になっちゃいそう…。ああっ、あああ…」
帆華の身体が、ガクガクと震え、腰が砕けた。すぐに四つん這いの姿勢をとっていることもできなくなり、
冴子の上に崩れ落ちた。慰安嬢が身に着けたテクニックの破壊力は、相手の男女を問わない。
冴子の上に崩れ落ちた。慰安嬢が身に着けたテクニックの破壊力は、相手の男女を問わない。
肌を密着させ重なり合う二人だが、舌を動かすことだけは止めなかった。
「いい、気持ちいいの…、また、イっちゃいそう…」
「私もよ…、イっちゃう……」
どちらからともなく、そんな言葉を何度も交わしては、交互に全身を痙攣させる。窓から差し込む月光に、
汗に濡れた二人の身体が輝いている。二人は、官能を貪るように腰を切なく揺らしながら、いつ果てるともな
く秘部を舐めあった。
汗に濡れた二人の身体が輝いている。二人は、官能を貪るように腰を切なく揺らしながら、いつ果てるともな
く秘部を舐めあった。
「ひい…、いいっ、いいい…、イくう…、ああああああ…」
帆華は、爪先をピンと伸ばし太股をガクガクと痙攣させた。
「ああっ、わたしも…。あうっ、あうっ、あああ…。いい、イくううう…」
同時に、冴子も喘ぎ声を漏らした。部屋の中に二人の喘ぎ声が響き渡った。二人は、肌を重ねあったまま絶
頂に達した。
頂に達した。
やがて、ベッドから起き上がろうとした冴子に、帆華が全身でしがみついてきた。
「ああ…、行かないで、このまま朝まで抱いてて…」
「わかりました…」
冴子がにっこり笑って答えると、帆華が甘えるように抱き着いてきた。
このワガママ娘との間で、冴子はついに精神的優位を勝ち取れたようだ。皮肉なことに、冴子が嫌悪した館
の訓練が、ここに来て彼女の切り札になった。
の訓練が、ここに来て彼女の切り札になった。
翌日の練習は、日本からやってきたマスコミ陣に公開されることになった。
レギュラーの荷物運びはいつもと同じだが、こういう時はさすがに、クラブハウス入口でのお迎えはない。
練習中もテニスウエアを着ることができた。
練習中もテニスウエアを着ることができた。
新聞や雑誌のカメラが並ぶ前で、冴子は帆華を相手に練習試合を披露する。
「サーティ・ラブ!」
冴子のコートにボールが転がり、帆華がガッツポーズを見せた。得意げな彼女の表情を集まったカメラが納
めていく。
めていく。
冴子の役割は、帆華の引き立て役だ。サーブは相手が得意なコースに確実に打ち込み、レシーブはわざと無
駄な動きをして、ギリギリ失敗して見せる。
駄な動きをして、ギリギリ失敗して見せる。
帆華が打って来た何でもないボールを、冴子は失敗を装って受け損ね、派手にコートに転がって両脚を開
き、無様にアンスコの股間を取材陣に披露した。
き、無様にアンスコの股間を取材陣に披露した。
「おおっ!」
「思わぬハプニング」だと思ったマスコミ陣から思わず声があがるとともに、シャッターが切られ、ビデオ
が回される。こうしたサービスもすべて打ち合わせどおりだ。
が回される。こうしたサービスもすべて打ち合わせどおりだ。
冴子は取材陣に素早く目を走らせた。
(いたっ…!)
大手の記者たちに押しのけられるように、端の方に豊橋樹里が立っていた。その横では、背の高い赤毛のイ
ギリス人男性が腕組みをしながら、こちらを見ている。スポーツはもちろん、それ以外の分野にも幅広い人脈
を持っているフリー・ジャーナリストのアンソニー・テイラー、樹里が冴子からもたらされる情報の提供先と
して選んだ相手だ。
ギリス人男性が腕組みをしながら、こちらを見ている。スポーツはもちろん、それ以外の分野にも幅広い人脈
を持っているフリー・ジャーナリストのアンソニー・テイラー、樹里が冴子からもたらされる情報の提供先と
して選んだ相手だ。
二人の姿を確認した冴子は、以後、努めてそちらの方を見ないように、八百長試合に集中した。
帆華がサーブを打ち込む。冴子は、わざと空振りやミスを繰り返し、帆華がサービスエースを連発している
かのように装う。
かのように装う。
「どうしたのかしら…、冴子、調子が悪いみたい…」
心配そうに呟く樹里の隣で、テイラーが囁いた。
"これは、八百長のようだね…"
"えっ?"
"冴子の表情と、筋肉の動きを見ていればわかる…"
練習試合で八百長をするというのは、一体どういうことだろう。不安と懸念を抱きながら、樹里はコートを
見つめた。
見つめた。
相手が無理なく返球できるコースに返して激しいラリーを装い、冴子は接戦の末に打ち負けたかに見せかけ
た。打ちひしがれた様子でコートに膝をつき、四つん這いになってガックリ項垂れる冴子、アンスコを割れ目
にしっかり食い込ませたそのお尻は、しっかりとマスコミのカメラのアングルを考えて突き出される。
た。打ちひしがれた様子でコートに膝をつき、四つん這いになってガックリ項垂れる冴子、アンスコを割れ目
にしっかり食い込ませたそのお尻は、しっかりとマスコミのカメラのアングルを考えて突き出される。
「那珂選手を打ち負かすなんて、力をつけましたね?」
試合を終えると、大手スポーツ新聞の記者が代表して帆華にインタビューする。
「ふふっ、違うわ、これが実力の差よ」
カメラに向かってニッコリ笑いながら、帆華が答えた。ここでも引き立て役の冴子が横に並んでいる。
「那珂選手はどうですか?」
「ここで、選手の皆さんと一緒に練習するようになって、ジュニアのようにはいかないなと実感しました…」
マスコミの取材に対して、冴子は他のメンバーを褒め、自分の未熟さを反省する。
「那珂選手は、これまで有力選手として注目されてきましたよね。有岡美奈選手たちとともに、女子テニスブ
ームの中心になっていた…」
ームの中心になっていた…」
記者が美奈の名前を出すと、報道陣の一部がざわついた。
「有岡…、あの反愛国者か!」
吐き捨てるように言ったのは、政府の提灯記事を専門に載せている右寄りの雑誌の記者だった。名前をもじ
って「スシロー」とあだ名される彼は、首相と毎週のように高級寿司店で酒を酌み交わす仲として有名であ
る。今回は、彼のような政府系プロパガンダ中心の記事を書いている記者も多数同行している。
って「スシロー」とあだ名される彼は、首相と毎週のように高級寿司店で酒を酌み交わす仲として有名であ
る。今回は、彼のような政府系プロパガンダ中心の記事を書いている記者も多数同行している。
「それなのに、補欠というのは悔しくないですか?」
静かにするよう目顔で制しながら、記者がインタビューを続けた。
「私など、まだまだ実力不足なので、補欠に選ばれただけでも光栄です。今回出場する選手の方たちから、ひ
とつでも多くの事を学びたいと思います」
とつでも多くの事を学びたいと思います」
そこまで言うと、冴子は帆華に「憧れ」の眼差しを向けた。
「特に赤坂選手のプレーはすばらしいです。自分も彼女のような選手を目指したいと思います」
しおらしくそう言う冴子を見て、帆華が満面の笑みを浮かべた。
|
|