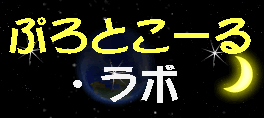イギリスの校外にある小さな町は、「ジュニア・トーナメント・テニス」のポスターがあちこちに張り出さ
れ、お祭りを前にした華やかな雰囲気に包まれていた。
れ、お祭りを前にした華やかな雰囲気に包まれていた。
今回のトーナメントは、伝統ある大会というよりは、単発のイベント的なものである。そうは言っても、世
界中から次代を担う有力選手が集まるとあって、大きな注目を集めていた。一昨年から準備されてきた大会
は、もはや単なる「お祭り」ではなく、そこでの成績はこれからテニス選手として活動していくうえでの大き
な実績になる。
界中から次代を担う有力選手が集まるとあって、大きな注目を集めていた。一昨年から準備されてきた大会
は、もはや単なる「お祭り」ではなく、そこでの成績はこれからテニス選手として活動していくうえでの大き
な実績になる。
スター選手、有岡美奈の登場で、日本でも数年前から女子の高校テニスが世間的に脚光を浴びるようになっ
たが、彼女たちの多くは高校に通いながらジュニアの世界で活躍しており、プロ選手の登録はまだしていなか
った。
たが、彼女たちの多くは高校に通いながらジュニアの世界で活躍しており、プロ選手の登録はまだしていなか
った。
父がプロ選手で、自分も高校と所属クラブの両方で活動し、実績も十分だった那珂冴子は、このトーナメン
トに出場し、その成績をひっさげて、プロのテニス選手になることを想定していた。美奈、千春、朋美といっ
たライバルたちも同じ道を描いていたはずである。
トに出場し、その成績をひっさげて、プロのテニス選手になることを想定していた。美奈、千春、朋美といっ
たライバルたちも同じ道を描いていたはずである。
明るい色調の躍動感あふれるポスターを見つめながら、冴子は小さなため息をついた。ライバルたちと一緒
に思い描いていた夢が無残に押しつぶされたことが、心に重くのしかかる。彼女の両手には、食材や衣類、雑
誌など、他の選手たちから買ってくるように指示された大量の荷物がぶら下がっていた。
に思い描いていた夢が無残に押しつぶされたことが、心に重くのしかかる。彼女の両手には、食材や衣類、雑
誌など、他の選手たちから買ってくるように指示された大量の荷物がぶら下がっていた。
大都市でも観光地でもないこの町にあるホテルは数が限られており、各国の選手たちは、にわか仕立てで宿
泊できるようにした公共施設や、住民から提供された家屋で寝泊まりして、大会に参加することとなった。経
済力がある日本選手団は、トーナメント会場の近くに、日本なら豪邸と言ってよい広さを持った民間の家を借
りることができ、そこで合宿生活を送っている。
泊できるようにした公共施設や、住民から提供された家屋で寝泊まりして、大会に参加することとなった。経
済力がある日本選手団は、トーナメント会場の近くに、日本なら豪邸と言ってよい広さを持った民間の家を借
りることができ、そこで合宿生活を送っている。
「お帰りなさい、次はトイレの掃除をお願いね。その後は、ユニフォームの洗濯をするのよ」
宿舎に戻って来た冴子を待ち構えていたように、女子選手団の主将、赤坂帆華が言った。日本から来ている
女子選手は6名、しかし、出場権は5名分しかない。冴子はいわば補欠扱いで参加し、小間使いのように他の
選手たちの雑用を押し付けられていた。
女子選手は6名、しかし、出場権は5名分しかない。冴子はいわば補欠扱いで参加し、小間使いのように他の
選手たちの雑用を押し付けられていた。
「そのために、連れて来てあげたんだから」
帆華の顔に意地悪な笑みが浮かぶ。目がパッチリしたコケテッシュな美人ではあるのだが、ワガママな性格
が立ち居振る舞いに滲み出ている。男性からはちやほやされるが、同性からはあまり好かれないタイプだ。し
かし、ここでは、選手もスタッフも誰もが女王のように彼女をもてはやし、彼女に従っている。なにしろ、帆
華は全日本テニス連盟理事長赤坂良徳の一人娘なのだ。
が立ち居振る舞いに滲み出ている。男性からはちやほやされるが、同性からはあまり好かれないタイプだ。し
かし、ここでは、選手もスタッフも誰もが女王のように彼女をもてはやし、彼女に従っている。なにしろ、帆
華は全日本テニス連盟理事長赤坂良徳の一人娘なのだ。
「はい、わかりました」
端正な美貌に浮かべたクールな表情を崩さず、口答え一つすることなく返事をする冴子を、帆華が満足げな
表情で見つめる。
表情で見つめる。
同世代のテニス少女たちがマスコミでとりあげられる中、父の影響で幼い時からテニスの練習をしてきた帆
華には強烈な嫉妬心が湧き起こった。実力も実績も、彼女たちの足元にも及ばない事実を直視することができ
ず、自分こそが、テニス少女ブームの中心にいるべきだという思いが日に日に肥大していく中で、帆華に三つ
の目標が生まれた。
華には強烈な嫉妬心が湧き起こった。実力も実績も、彼女たちの足元にも及ばない事実を直視することができ
ず、自分こそが、テニス少女ブームの中心にいるべきだという思いが日に日に肥大していく中で、帆華に三つ
の目標が生まれた。
それは、第一に、帆華自身がトーナメントに出場して脚光を浴びること、第二に、那珂冴子を側に侍らせる
ことだった。同世代の選手たちの中で、クールビューティの冴子に対しては、お気に入りのアイドルに感じる
ような、恋愛に似た気持ちを抱いたのである。そして、最後に、プリンセスを「僭称」する偽物、有岡美奈を
テニス界から抹殺することであった。
ことだった。同世代の選手たちの中で、クールビューティの冴子に対しては、お気に入りのアイドルに感じる
ような、恋愛に似た気持ちを抱いたのである。そして、最後に、プリンセスを「僭称」する偽物、有岡美奈を
テニス界から抹殺することであった。
それらの目標達成のために帆華がやったことは、練習を積むことでも、技術を磨くことでもなく、ひたすら
父の権力を借ることだった。
父の権力を借ることだった。
「冴子、逃げちゃダメよ、わかってるわよね」
そう言いながら、帆華は冴子のスカートを捲りあげた。そこにはステンレス製の貞操帯がはめられていた。
「こうしておかないと、冴子はどこかに行っちゃうでしょ?」
甘えるような声を出して、帆華が逃がさないとばかり、冴子の手をギュッと握った。
「ああっ!」
ふいに股間を襲った衝撃に冴子が両手で下腹部を押さえ、前屈みになって身悶えする。貞操帯の中の冴子の
膣内には、リモコン式のバイブが埋め込まれているのだ。
膣内には、リモコン式のバイブが埋め込まれているのだ。
「うっ、ううっ…」
お尻を振り、身体を震わせて耐える冴子の目の前で、帆華は手にしたリモコンを操作して見せた。下腹部に
伝わる振動がさらに強くなり、クネクネとした動きが膣内をかき回す。
伝わる振動がさらに強くなり、クネクネとした動きが膣内をかき回す。
「あっ、あ…ああっ、ああん…」
冴子の身体が痙攣したように震え、そしてふっと力が抜ける。軽いアクメを迎えたらしい。
「あらっ、冴子、イっちゃったの?」
コロコロと笑いながら、帆華がポケットから貞操帯の鍵を取り出し、冴子の股間を覆うステンレスを外し
た。そして、陰部から顔を出しているバイブを握り、冴子の体内から引き出していく。
た。そして、陰部から顔を出しているバイブを握り、冴子の体内から引き出していく。
「あ、ああぁ…」
肉襞を擦られて、冴子が喘ぎ声を漏らす。ゆっくりと取り出されたのは、エラが大きく反り返った男性器そ
っくりの赤黒いバイブだった。スイッチが入ったままになっているために、モーター音を立てて振動し、クネ
クネとくねるように回転している。ずっと膣内に入っていたそれは、冴子の愛液でヌルヌルに光っていた。
っくりの赤黒いバイブだった。スイッチが入ったままになっているために、モーター音を立てて振動し、クネ
クネとくねるように回転している。ずっと膣内に入っていたそれは、冴子の愛液でヌルヌルに光っていた。
帆華がその場にしゃがんで、冴子の股間を覗き込んだ。さっきまでバイブを咥えていた、割れ目はお漏らし
をしたように濡れており、少し開いた陰唇の奥で、媚肉が蠢いている。
をしたように濡れており、少し開いた陰唇の奥で、媚肉が蠢いている。
「すごく濡れてるわよ」
帆華が楽しげに笑い、指先が恥丘の周りをゆっくりとなぞっていく。冴子の口から喘ぎ声が漏れる。帆華は
愛液で濡れた秘孔に指を差し込んだ。
愛液で濡れた秘孔に指を差し込んだ。
「うっ、いっ…、いい…」
帆華が再びバイブのスイッチを入れ、冴子の股間に近づける。包皮を掻き分けちょこんと顔を出した真珠色
の突起がバイブの振動で責められる。
の突起がバイブの振動で責められる。
「はうっ、ああぁ…」
切なげな声を漏らして冴子が腰を揺すり、濡れて光る女陰からツーッと糸を引いて、愛液が床へ滴り落ち
た。グイッと力を入れると、バイブのカリの部分が冴子の割れ目を押し広げる。
た。グイッと力を入れると、バイブのカリの部分が冴子の割れ目を押し広げる。
「ううっ、うう…」
クネクネと動くバイブが再び、冴子の中に入って来た。
バイブを奥まで挿入すると、帆華は再び貞操帯を装着する。
ベルトタイプの貞操帯を嵌め、小陰唇を指先で引っ張ってスリットから絞り出すように露出させる。こうし
ておかないと、排尿の際に尿が内部に溜まって不衛生だし、おしっこがスムーズにできないからだ。そこに、
いくつもの穴があいた板をかぶせた。
ておかないと、排尿の際に尿が内部に溜まって不衛生だし、おしっこがスムーズにできないからだ。そこに、
いくつもの穴があいた板をかぶせた。
きちんと装着されたことを確認して、帆華は貞操帯の鍵をかけてポケットに入れた。メーカーの説明による
と、鍵がなければ、この貞操帯は、本人がいくら工具を使って外そうと試みても外れないのだと言う。帆華が
鍵を開けないかぎり、冴子は自分の下腹部に触ることができず、体内に埋め込まれたバイブを抜くこともでき
ない。お風呂に入る時も眠る時も貞操帯をつけたままで、排泄もステンレスに開けられた小さな穴からするし
かない。
と、鍵がなければ、この貞操帯は、本人がいくら工具を使って外そうと試みても外れないのだと言う。帆華が
鍵を開けないかぎり、冴子は自分の下腹部に触ることができず、体内に埋め込まれたバイブを抜くこともでき
ない。お風呂に入る時も眠る時も貞操帯をつけたままで、排泄もステンレスに開けられた小さな穴からするし
かない。
これは、逃走防止の意味もあるが、それ以上に帆華の独占欲と趣味という部分が大きかった。
「これ、明日の買い物リストよ、私たちが練習している間に買っておいてね。わかった?」
そう言うと、帆華はようやくバイブのスイッチを切り、メモ帳に書いたリストを半ば放り投げるようにし
て、自分の部屋に帰っていった。
て、自分の部屋に帰っていった。
残された冴子がバイブで刺激された後の呼吸を整えていると、入口の呼び鈴が鳴った。ドアを開けると、1
0歳ぐらいの可愛らしいブロンドの少女が立っていた。
0歳ぐらいの可愛らしいブロンドの少女が立っていた。
"Hello!"
ニッコリ笑って挨拶をした少女は、近くの雑貨屋の娘である。この店で買った物は冴子が持って帰ることも
あれば、こうして届けてもらうこともある。少女が持ってきた商品を受け取ると同時に、一瞬の隙を縫うよう
に少女の手から冴子の手に小さな紙片が滑り込む。
あれば、こうして届けてもらうこともある。少女が持ってきた商品を受け取ると同時に、一瞬の隙を縫うよう
に少女の手から冴子の手に小さな紙片が滑り込む。
"Thank you"
チップを受け取った少女が笑顔で去っていく背中を見ながら、冴子は渡された紙片に視線を走らせた。そこ
には、日時と場所だけが旧知のスポーツ・ジャーナリスト豊橋樹里の筆跡で走り書きされていた。
には、日時と場所だけが旧知のスポーツ・ジャーナリスト豊橋樹里の筆跡で走り書きされていた。
「帆華、今夜、冴子を貸してもらっていいか?」
夕食の時間に、そう尋ねたのは男子選手団の主将、須崎雅裕だった。苗字からわかるとおり、彼の伯父は時
の権力者、内閣総理大臣の須崎晋次だ。
の権力者、内閣総理大臣の須崎晋次だ。
「グラビアとか見てたら、ムラムラしちゃってよ」
雅裕の隣にいた男子がそう言って、ニヤニヤ笑った。帆華が顔を顰めて見せる。
「ホントに、あんたたちって、エッチね」
「仕方ないだろ、男の本能だよ」
そう言いながら、雅裕がニヤニヤ笑い、給仕役をしている冴子にいやらしい視線を投げる。
冴子は星園テニス部のユニフォームを着ていた。ノーブラの胸が薄い生地に乳房の形を映し出し、身動きす
る度に、短いスコートから貞操帯のステンレスや剥き出しのお尻がチラチラと覗いている。全員で5人いる男
子選手や、同席した男のスタッフたちが、卑猥な視線を彼女に投げかける。
る度に、短いスコートから貞操帯のステンレスや剥き出しのお尻がチラチラと覗いている。全員で5人いる男
子選手や、同席した男のスタッフたちが、卑猥な視線を彼女に投げかける。
ここでの冴子の役割は雑用係だけではない、男子選手団やスタッフの性欲処理もさせられているのだ。もち
ろん、その際には「所有者」である帆華の了解をとる必要がある。
ろん、その際には「所有者」である帆華の了解をとる必要がある。
「じゃあ、今夜は私も参加するわ」
「えっ、帆華も俺たちの相手をしてくれるのか?」
雅裕が驚いた表情を浮かべると、帆華が笑い声をあげた。
「するわけないでしょ、あんたたちごときに」
侮蔑するような口調で帆華がそう言い放った。須崎雅裕は、本来は海外トーナメントに選ばれるようなレベ
ルの選手ではない。それが、コネで選手団に入ったところは、帆華と立場がよく似ている。ただ、本格的にテ
ニスをやってきたと自負している帆華の方はそうは思っておらず、彼のことを一段下に見下したようなところ
があるのだ。
ルの選手ではない。それが、コネで選手団に入ったところは、帆華と立場がよく似ている。ただ、本格的にテ
ニスをやってきたと自負している帆華の方はそうは思っておらず、彼のことを一段下に見下したようなところ
があるのだ。
(ホントに、生意気な女だよな…)
本来、プライドが高い雅裕がそれを我慢して、ヘラヘラしているのは、帆華が女子で、それなりに美人だか
らだ。そして、それ以上に、テニスをやっているなら、彼女をちやほやしていれば、メリットが大きい。例え
ば、この選手団に選ばれ、冴子の身体を玩具にできるといったように。
らだ。そして、それ以上に、テニスをやっているなら、彼女をちやほやしていれば、メリットが大きい。例え
ば、この選手団に選ばれ、冴子の身体を玩具にできるといったように。
そんなバカバカしい選手たちを心の中で軽蔑しながら、冴子は内心を悟られないようにポーカーフェイスで
黙々とつきあっている。屈辱的な日々を我慢してでも、館の監視が行き届かない海外に出られたことは、彼女
の計画にとって非常に大きなチャンスなのだ。
黙々とつきあっている。屈辱的な日々を我慢してでも、館の監視が行き届かない海外に出られたことは、彼女
の計画にとって非常に大きなチャンスなのだ。
食事係の現地スタッフに混じって料理を運んでいる冴子のお尻を、誰かがすれ違いざまに撫でていく。振り
返ると、男性スタッフの一人がニヤニヤ笑いながら、こっちを見ていた。
返ると、男性スタッフの一人がニヤニヤ笑いながら、こっちを見ていた。
(これが、もし美奈だったら、怒りで爆発したかもしれないな…)
真っ直ぐな気性の親友のことをすこし羨ましく思い出しながら、冴子はふとそんなことを考えた。
食後、カメラやビデオを持った男子たちの前で、全裸になった冴子がソファに腰かけ、M字開脚の姿勢をと
った。大きく脚を開くのを見て、まだ少年と言ってよい5人の男子選手が揃って歓声をあげ、大喜びで手を叩
いた。
った。大きく脚を開くのを見て、まだ少年と言ってよい5人の男子選手が揃って歓声をあげ、大喜びで手を叩
いた。
現地に来てから買った無修正のグラビアに触発された彼らは、冴子をモデルにした撮影会を行うことになっ
たのだ。
たのだ。
クールビューティと称えられた端正な顔立ちの美少女が、男子たちの前に秘所を晒していた。選手たちがさ
っきまで興奮して眺めていたグラビアのセクシーモデルよりも、目の前にいる冴子の方が数倍美しい。
っきまで興奮して眺めていたグラビアのセクシーモデルよりも、目の前にいる冴子の方が数倍美しい。
陰毛をきれいに剃られた色白の土手の膨らみは、それほど高くなく、割れ目がぴっちりと閉じ合わされてい
る。大人っぽい雰囲気の冴子だが、女陰の色や形はむしろ清楚で、幼い少女のように見える。明るい照明の下
で男子に食い入るように覗き込まれて、さすがに恥ずかしいらしく、色白の頬を染めた冴子は、彼等から視線
を逸らせていた。
る。大人っぽい雰囲気の冴子だが、女陰の色や形はむしろ清楚で、幼い少女のように見える。明るい照明の下
で男子に食い入るように覗き込まれて、さすがに恥ずかしいらしく、色白の頬を染めた冴子は、彼等から視線
を逸らせていた。
いかにも高級そうな一眼レフを構える雅裕の横で、冴子にスマホを向け、その恥ずかしい姿を熱心に撮影し
ている飯森利次は、幼い頃から活動しているテニス選手で、冴子とは旧知の間柄だ。今回の男子の中では、実
力にもとづいて順当に選考されたと言える選手なのだが、ここに来てすっかり羽目を外していた。とりわけ、
冴子を相手に筆おろしをしてからは、すっかりセックスに嵌り、雅裕たちと「同じ穴の狢」になってしまって
いる。
ている飯森利次は、幼い頃から活動しているテニス選手で、冴子とは旧知の間柄だ。今回の男子の中では、実
力にもとづいて順当に選考されたと言える選手なのだが、ここに来てすっかり羽目を外していた。とりわけ、
冴子を相手に筆おろしをしてからは、すっかりセックスに嵌り、雅裕たちと「同じ穴の狢」になってしまって
いる。
「アソコを自分で開いて見せなさいよ」
ビデオカメラを構えた帆華が命令する。
「…はい…」
冴子は、両手の指を大陰唇にかけて、ゆっくりと膨らみを開いていった。対になった舟形の膨らみが丸く開
き、ピンク色の唇の裏側と、さらに濃い肉色の粘膜が露わになった。指先でさらに大きく開くと、淡いピンク
の肉襞に縁どられた秘孔がワナワナと蠢いていた。割れ目の上部には三角形のフードの下でつやつやと輝くク
リトリスが顔を覗かせている。
き、ピンク色の唇の裏側と、さらに濃い肉色の粘膜が露わになった。指先でさらに大きく開くと、淡いピンク
の肉襞に縁どられた秘孔がワナワナと蠢いていた。割れ目の上部には三角形のフードの下でつやつやと輝くク
リトリスが顔を覗かせている。
これほど間近で、隅々まで女性器を観察する機会はめったにない。好奇心を剥き出しにした男子たちは、夢
中でカメラに収めていく。
中でカメラに収めていく。
「次は、手を床について、四つん這いになるのよ」
帆華に指示されて、ソファから降りた冴子が掌と膝を床につけた。ゆっくりと膝を伸ばすと、男子たちに向
かってお尻を突き出す格好になる。
かってお尻を突き出す格好になる。
「へへっ、いい眺めだ」
「ケツの穴まで丸見えだぞ。冴子」
男子たちが口々に卑猥な感想を述べて、冴子を言葉で嬲る。
雅裕が手を伸ばして、人差し指を秘孔の中に入れた。膣が収縮し、熱を持った襞肉が指に絡みついてくる。
雅裕が指を折り曲げて襞肉をかき回し、膣奥の天井を指の腹で擦った。
雅裕が指を折り曲げて襞肉をかき回し、膣奥の天井を指の腹で擦った。
「ああっ…」
冴子の声とともに、溢れ出た愛液が太腿を伝った。
「すげぇー。オ××コ、濡れ濡れだ。太腿を伝って流れてるぞ」
飯森が驚いたような声をあげる。
「クールな那珂冴子が、こんなに淫乱だったなんて…、なぁ」
雅裕の言葉に、男子たちが卑猥な笑い声を立てる。次々に浴びせられる屈辱的な言葉に、冴子は思わず唇を
ギュッと噛み締め、顔を朱に染めた。
ギュッと噛み締め、顔を朱に染めた。
「そんなにセックスしたいなら、入れてやるよ」
そう言って雅裕が立ち上がる。振り返ると、ズボンとパンツを脱いだ雅裕の股間に、黒々とした茂みから赤
黒い怒張が天井を向いて屹立していた。
黒い怒張が天井を向いて屹立していた。
雅裕は、掲げられた冴子のお尻を両手で掴み左右に割った。雅裕の怒張が割れ目をなぞっていく。
「ああ、あああ…、ああ…」
冴子が喘ぎ声を上げる。雅裕は、ニヤニヤ笑いながら冴子の中に亀頭を潜り込ませた。
「ああ、いっ、いい…、ああああ…」
冴子が腰をクネクネと揺すりながら、雅裕の怒張を秘孔の奥深くに導いていく。
「あっ、うっ、ああぁん…」
悩ましげな喘ぎ声とともに四つん這いの姿勢で自ら腰を振り、冴子は膣壁で雅裕の肉棒を擦りたてた。男が
じっとしていても、自らが動いて快感を与えるのが慰安嬢のセックスの基本である。
じっとしていても、自らが動いて快感を与えるのが慰安嬢のセックスの基本である。
グチュッ、グチュッ、グチュッ…。
濡れた粘膜が擦れ合う音が部屋に篭る。
バコッ、バコッ、バコッ…。
冴子の双尻が雅裕のお腹を叩いている。
そのままでも十分気持ち良かったが、女を攻めて快楽を追求したいという男の本能が湧き起り、雅裕は自ら
腰を動かし始めた。
腰を動かし始めた。
「ううっ、ううう…いい、い、いいいい…」
後ろから突かれ、冴子が背を退け反らせて喘ぐ。秘孔が雅裕の怒張を締め上げた。
「冴子、いい格好。とってもいやらしいわよ」
四つん這いになり、後ろから獣のように犯される冴子の姿を、帆華が嬉々として撮影していく。
「うっ…、出るっ!」
雅裕が呻き声を漏らし、冴子の中にビクビクと射精する。権力者の子弟である男子選手たちを受け入れるの
に、コンドームの使用など認められるはずがなかった。
に、コンドームの使用など認められるはずがなかった。
冴子の膣内にありったけの精液をぶちまけた雅裕に代わって、飯森が冴子の割れ目に怒張をあてがい一気に
突き刺した。
突き刺した。
「うっ、いい…」
飯森はゆっくりと怒張を抜き差しする。飯森の肉棒に押し出された雅裕の精液が、冴子の太股を伝い白い筋
を作っている。
を作っている。
「ああ…、い、いいの…」
冴子がよがり声をあげる。飯森は冴子の胸に手を廻し、双乳を揉みしだいた。乳首を指で強く摘まみ、怒張
を冴子の奥深くに突き込む。冴子は腰をくねらせながら絶頂の前の高ぶりを感じている。
を冴子の奥深くに突き込む。冴子は腰をくねらせながら絶頂の前の高ぶりを感じている。
「あはぁ、も、もっと…」
飯森が怒張を冴子の奥深くに突き込む。汗で髪が頬に張り付いた顔を揺すりながら、冴子が喘ぎ声をあげ
る。
る。
「掃除してくれよ」
雅裕が冴子の前に仁王立ちになり、彼女の顔の前で、精液まみれの肉棒を片手で持ってぶらぶらさせた。
「はい…」
冴子が舌を伸ばし、雅裕の怒張に絡めていく。鈴口を舌で突付き、カリの裏側へと舌を這わせ、精液をきれ
いに舐め取っていった。
いに舐め取っていった。
雅裕の肉棒が冴子の唇を割り、口の中に滑り込んだ。冴子は腰を振りながら、頬をすぼませ、尿道に残った
精液を吸いだした。コクンコクンと喉が動き、男の体液を呑み込む様子を帆華がビデオに収めていく。
精液を吸いだした。コクンコクンと喉が動き、男の体液を呑み込む様子を帆華がビデオに収めていく。
「う、うっ、ううっ…」
バックで冴子と繋がっている飯森が気持ちよさそうな呻き声を漏らし、腰の動きを早めて一気に攻め立て
た。それに合わせて冴子の腰がうねる。バコン、バコンっとお尻を打つ音が響き渡る。
た。それに合わせて冴子の腰がうねる。バコン、バコンっとお尻を打つ音が響き渡る。
「あっ、あっ、ああぁっ…」
冴子の膣が収縮し、男の怒張を絞り上げた。キュッ、キュ、キュッと強く弱く締め上げる。
「ううっ、ううう…」
官能の波に喘ぎ声をあげ頭を振る冴子に、飯森が言った。
「いいぞ、冴子のオ××コ…、すごい締め付けてくる…」
「ああ、ああぁ…、い、いくぅ…」
冴子は足の指先までツッパリ、体をガクガクと痙攣させる。飯森は最後の一打ちを打ち込み、冴子の中に精
液を吐き出した。同時に冴子も絶頂を迎える。荒い息を吐きながら、飯森が肉棒を抜くと、冴子は床に崩れる
ようにつっぷした。
液を吐き出した。同時に冴子も絶頂を迎える。荒い息を吐きながら、飯森が肉棒を抜くと、冴子は床に崩れる
ようにつっぷした。
「私も気持ち良くして」
とうとう我慢できなくなった様子で帆華がパンティを脱ぎ、冴子を仰向けにすると、その顔を跨いで腰を下
ろした。
ろした。
「ううっ…」
濡れた帆華の女陰で鼻と口を塞がれて、冴子が呻き声を漏らす。
「ああん、気持ちいい…」
なんとか呼吸しようと冴子が顔を左右に振る動きが刺激になり、帆華がよがり声をあげ、股間を冴子の鼻に
押し付けてくる。
押し付けてくる。
ようやく鼻で呼吸できるようになると、冴子は帆華の亀裂に舌を這わせた。
「ああぁ…」
冴子の前には、パックリと口を開いた帆華の陰部がある。冴子が舌の腹で擦り上げるように舐めると、帆華
の腰がブルッと震える。
の腰がブルッと震える。
「いいっ、もっと、もっとぉ…」
帆華が甘えるような声で催促する。亀裂の中で突起が真珠色に輝いている。冴子の舌が、尖り出している肉
芽をぺろりと舐めた。
芽をぺろりと舐めた。
「ううっ…」
帆華の身体が電気が走ったように震え、白い喉を伸ばして仰け反った。冴子の舌が、溢れ出る愛蜜をピチャ
ピチャと音を立てて掬い取る。その間にも冴子の性器に、次の男が入って来た。
ピチャと音を立てて掬い取る。その間にも冴子の性器に、次の男が入って来た。
「うっ、うん…。気持ちいい…、さすが慰安嬢…、すごい上手…」
帆華がうっとりした声で呟くのを聞いて、冴子はギュッと唇を噛んだ。
|
|