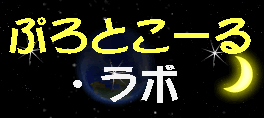テニスコートの周りに作られた観客用スタンドに、屈強な若い男たちが団体でやって来た。一団の先頭に立
って案内をしているのは、このところすっかり選手兼マネージャーの役割が定着してきた中西朋美だ。
って案内をしているのは、このところすっかり選手兼マネージャーの役割が定着してきた中西朋美だ。
「癒しの館での最初のアトラクションとして、皆様にはテニス部の練習を見学していただきます」
朋美が男たちに向かって言った。彼らは、魏国を対象としたアルメイア軍との共同作戦のために派遣される
防衛隊員たちである。
防衛隊員たちである。
世襲の独裁国家である魏国は、このところ核兵器やミサイルの開発を全世界に向けてアピールしている。国
際社会から孤立していることに焦りを覚えた三代目の若い指導者が、他国の協力や支援を引き出そうとして花
火を打ち上げているのが実態だが、彼が最大の交渉相手にしたいアルメイアも現大統領が超タカ派の変人であ
るためうまくいかず、双方が舌戦を繰り広げる中で、軍事的な緊張が高まっているのが今の実態である。日本
政府はいつものように、独自の情勢判断など念頭になく、ただちにアルメイアを支持し、魏国沿岸に共同で部
隊を配備することにしたのだ。
際社会から孤立していることに焦りを覚えた三代目の若い指導者が、他国の協力や支援を引き出そうとして花
火を打ち上げているのが実態だが、彼が最大の交渉相手にしたいアルメイアも現大統領が超タカ派の変人であ
るためうまくいかず、双方が舌戦を繰り広げる中で、軍事的な緊張が高まっているのが今の実態である。日本
政府はいつものように、独自の情勢判断など念頭になく、ただちにアルメイアを支持し、魏国沿岸に共同で部
隊を配備することにしたのだ。
状況次第では戦闘が開始され、生命の危険もあることから、全国の各部隊から選りすぐりの隊員が選ばれた
うえに、派遣に対する報酬の一つとして「星園癒しの館」で一泊二日の慰安を楽しむことが企画されたのであ
る。
うえに、派遣に対する報酬の一つとして「星園癒しの館」で一泊二日の慰安を楽しむことが企画されたのであ
る。
「おい…、見ろよ…」
「見てるよ…」
隊員たちがお互いを肘で突き合って、ニヤニヤ笑いを浮かべた。彼らの視線は、スケジュールを説明する朋
美の胸に注がれていた。デザインはお洒落で清楚なテニスウエアなのだが、薄手の生地がぴったりと身体にフ
ィットしている。それをノーブラで着ているために乳首の突起はもちろんのこと、乳房全体の形がくっきりと
浮き出ている。膨らみの頂点を彩る乳暈も白い生地に透けて、その大きさがはっきりとわかった。
美の胸に注がれていた。デザインはお洒落で清楚なテニスウエアなのだが、薄手の生地がぴったりと身体にフ
ィットしている。それをノーブラで着ているために乳首の突起はもちろんのこと、乳房全体の形がくっきりと
浮き出ている。膨らみの頂点を彩る乳暈も白い生地に透けて、その大きさがはっきりとわかった。
「みなさん…ご覧になっている、これが、星園テニス部の公式ユニフォームです」
食い入るような視線を感じて、朋美が頬を染めた。
「オッパイが見えちゃってるみたいで、ちょっと恥ずかしいのですが、見られる興奮が試合や練習での勢いに
つながるというのが館の方針なので、みんな頑張って着ています。スコートの長さも、股間ギリギリにするよ
う決まっているんですよ…」
つながるというのが館の方針なので、みんな頑張って着ています。スコートの長さも、股間ギリギリにするよ
う決まっているんですよ…」
隊員たちの目が一斉に、眩い白さを見せる太腿に注がれた。短いとは思っていたものの、言われてみれば確
かに、普通に立っていてさえも中のアンダースコートがチラチラ見えてしまっている。隊員たちの表情が卑猥
に緩んだ。
かに、普通に立っていてさえも中のアンダースコートがチラチラ見えてしまっている。隊員たちの表情が卑猥
に緩んだ。
派遣部隊を迎えるにあたっての、最初のアトラクションをテニス部が請け負うことになったのは、松川の鶴
の一声による。
の一声による。
テニス連盟の理事長選挙を有利にすすめるために部員たちを使いたいと考えた松川は、諸藤館長からその許
可を得ようとしたのだが、今もなお面会すらできない状態にあった。どうやら諸藤の不興を買ったようなのだ
が、どう考えても理由が思い当たらない。いや、正確に言えば、様々な理由が思いつくのだが、どれも決定的
なことではない気がする。途方に暮れた松川が頼ることにしたのは、南原事務局長だった。
可を得ようとしたのだが、今もなお面会すらできない状態にあった。どうやら諸藤の不興を買ったようなのだ
が、どう考えても理由が思い当たらない。いや、正確に言えば、様々な理由が思いつくのだが、どれも決定的
なことではない気がする。途方に暮れた松川が頼ることにしたのは、南原事務局長だった。
体育科の責任者で野心家の石堂しおりのもと政財界の接待の場に使われることが多くなった館の運営につい
て、南原は「防衛隊員のための慰安施設という原点をふまえた運営をすべきだ」と主張しており、その意向を
受けた松川は、派遣部隊の慰安をテニス部で積極的に引き受けることにしたのだ。
て、南原は「防衛隊員のための慰安施設という原点をふまえた運営をすべきだ」と主張しており、その意向を
受けた松川は、派遣部隊の慰安をテニス部で積極的に引き受けることにしたのだ。
「中西さんもそうだけど、星園テニス部って、有名な選手が多いよね」
隊員の一人がそう声をかけてきた。
「今年の4月に体育科を設置するにあたって館が目玉にしたのがテニス部で、全国から優秀な部員を集めまし
た。私も、…実家の事情があって、ここに転校してきたんです…」
た。私も、…実家の事情があって、ここに転校してきたんです…」
「おまえの親父、贈賄容疑で逮捕されたんだよな!」
別の隊員が嘲笑まじりにそう言った。面長で額が広く、頭は良さそうだが、それが底意地の悪さにつながっ
ているタイプだ。
ているタイプだ。
「反愛国会社だった中西産業を、新社長の叔父さんが立て直したんだろ…」
事情通を気取って話しつづける隊員に、周りの視線が集中する。
「そう言えば、そんなニュース、あったな」
誰かが相槌を打った。朋美は思わずギュっと唇を噛んだ。中西産業が「反愛国会社」のレッテルを貼られた
のは、むしろ父が政治献金を断ったためなのに、逆の事実がでっち上げられて巷に流されている。父の逮捕、
倒産の危機、そうした災厄はすべて新社長になった叔父が国防省の力を背景に行った謀略であり、その一環と
して、朋美はこの館に送られたのだ。
のは、むしろ父が政治献金を断ったためなのに、逆の事実がでっち上げられて巷に流されている。父の逮捕、
倒産の危機、そうした災厄はすべて新社長になった叔父が国防省の力を背景に行った謀略であり、その一環と
して、朋美はこの館に送られたのだ。
「そんなことより、見ろよ。さすが星園の慰安嬢、可愛い子が多いぜ!」
別の隊員の一言で、一団は準備体操をしている少女たちに目をやった。
いずれ劣らぬ美少女たちが、朋美と同じエロティックなテニスウエアを着て身体を動かしている。その体操
もどことなくセックスやオナニーを連想させる動きが多く、隊員たちは食い入るように見つめた。
もどことなくセックスやオナニーを連想させる動きが多く、隊員たちは食い入るように見つめた。
「今日はこれから、部員たちを紅白2チームに分け、対抗試合が行われますが、みなさんも紅白それぞれ、ど
ちらを応援するか決めていただきます…」
ちらを応援するか決めていただきます…」
朋美が説明を始めた。それは、企画を任されたコーチたちが相談して決めたアトラクションである。
「試合で、選手は1ゲームをとられる度に着ているものを脱いでいき、先に全裸になった方が負けです…」
説明を聞いた隊員たちの目が、卑猥に輝く。着ているものと言ってもシューズとソックスは対象外のため、
少女たちはウエア、スコート、アンスコの三つしか身につけていない。3ゲームを相手に取られると、脱ぐも
のがなくなって、負けになるのだ。
少女たちはウエア、スコート、アンスコの三つしか身につけていない。3ゲームを相手に取られると、脱ぐも
のがなくなって、負けになるのだ。
「全メンバーの試合が終わった段階での勝敗数を競い、勝ち負けを決めます。負けたチームの選手たちは罰ゲ
ームとして、勝ったチームを応援していただいたみなさんの性欲を、この場で処理しなければならなりませ
ん。順番にはなりますが、フェラチオもセックスも、お好きなだけ楽しんでいただけます」
ームとして、勝ったチームを応援していただいたみなさんの性欲を、この場で処理しなければならなりませ
ん。順番にはなりますが、フェラチオもセックスも、お好きなだけ楽しんでいただけます」
「おおっ!」
隊員たちが驚きと喜びの声をあげた。慰安施設だということで、それなりのことは期待してきたところだ
が、いきなりの過激なサービスは想定外だった。しかも、慰安嬢は聞きしに勝る美少女揃いだ。
が、いきなりの過激なサービスは想定外だった。しかも、慰安嬢は聞きしに勝る美少女揃いだ。
「第一試合は、紅組が1年、菱田由加理、白組は同じく1年の岡崎里穂!」
玉田コーチの甲高い声がコートに響き、二人の少女がコートに入って来た。二人とも落ち着かない様子で、
隊員たちで埋まった観客席を不安げに見回している。
隊員たちで埋まった観客席を不安げに見回している。
「彼女たちは、二週間ほど前に館に来たばかりの転入生です。スタイルが良く、キリッとした端正な顔立ちの
菱田、ふんわりした女の子っぽい可愛らしさを見せる岡崎、タイプの違う二人は、ほんの少し前まで普通の女
子高生でした」
菱田、ふんわりした女の子っぽい可愛らしさを見せる岡崎、タイプの違う二人は、ほんの少し前まで普通の女
子高生でした」
コートに設置されたスピーカーから聞こえてくるのは、審判台の横に作った「放送席」で女子アナを気取っ
ているテニス部コーチ、原田晴亜の声だ。
ているテニス部コーチ、原田晴亜の声だ。
「男の子とつきあったこともなかった二人ですが、この館に来て国家に処女を捧げ、身体のあらゆる部分を使
って男性を満足させることを学んでいます。時には涙し、日々、恥ずかしさとたたかいながら一人前の慰安嬢
を目指す、その初々しい姿をお楽しみください」
って男性を満足させることを学んでいます。時には涙し、日々、恥ずかしさとたたかいながら一人前の慰安嬢
を目指す、その初々しい姿をお楽しみください」
晴亜のあざといアナウンスを聞いて、隊員たちが大きな喚声をあげた。
「ザ ベストオブ 1セットマッチ 岡崎 トゥ サーブプレイ!」
審判を務める玉田のコールが響いた。
「…どこにいるのかな…」
隊員の一人、海上防衛隊所属の前田一等隊士は、試合を始めた二人ではなく、出番を控える選手たちを、目
を凝らして見つめていた。彼自身、中学・高校とテニスをやってきたのに加えて、女子テニス選手ブームに熱
中したファンの一人だった。そんな彼のお目当てはズバリ、テニス界のプリンセス、有岡美奈以外にはあり得
ない。
を凝らして見つめていた。彼自身、中学・高校とテニスをやってきたのに加えて、女子テニス選手ブームに熱
中したファンの一人だった。そんな彼のお目当てはズバリ、テニス界のプリンセス、有岡美奈以外にはあり得
ない。
しかし、選手のひとり一人を丹念に見ていっても、美奈の姿は見当たらなかった。
「ここにいるはずなんだけど…」
そう呟きながら、ふとコートの隅に目をやると、一人の少女が黙々と球拾いをしていた。
「あれ…、あの子、試合に出ないのかな?」
前田が首を捻った瞬間、周りの隊員たちが大きな歓声を上げた。見ると、スタンド席の前に岡崎里穂が立っ
ている。どうやら、1ゲーム取られたらしい。
ている。どうやら、1ゲーム取られたらしい。
「最初に、アンダースコートを脱ぎます」
晴亜がアナウンスを通じて指示するのを聞いて、里穂の顔が強張った。最初に脱ぐならスコートからだと考
えていたが、甘かったようだ。スコートの中に手を入れ、アンスコの腰に指をかけてはみたものの、なかなか
下げることが出来ない。思い切りが肝心だと思うのだが、その勇気がない。スタンドにいる何十人もの男たち
の視線が、自分に注がれているのを感じて、ますます身体が硬くなる。
えていたが、甘かったようだ。スコートの中に手を入れ、アンスコの腰に指をかけてはみたものの、なかなか
下げることが出来ない。思い切りが肝心だと思うのだが、その勇気がない。スタンドにいる何十人もの男たち
の視線が、自分に注がれているのを感じて、ますます身体が硬くなる。
「さあ、5秒以内に脱がないと、負けとみなして全部脱いでもらうわよ!」
脅すような晴亜の声に、里穂は慌てて腰をかがめるようにして、アンスコを足元から抜き取った。剥き出し
のお尻を風が嬲っていく感触に、思わず頬が火照る。
のお尻を風が嬲っていく感触に、思わず頬が火照る。
スコートの裾を両手で庇うようにして、観客に一礼すると里穂はコートに戻って行った。その様子を、球拾
いの少女がじっと見つめている。
いの少女がじっと見つめている。
「やっぱりそうだ!」
前田が思わず声をあげた。それは間違いなく、有岡美奈その人であった。
(どうしよう…)
そう思いながら、由加理はとりあえず、素直なコースでボールを返した。同じ転入生とは言っても、部活で
頑張ってテニスをやっていた程度の里穂と、プロ選手を目指して英才教育を受けて来た由加理では、力量に雲
泥の差がある。由加理がその気になれば、あっと言う間に勝負はついてしまうだろう。しかし、それによって
里穂が素っ裸にされ、男たちの見世物にされるのは、由加理には耐え難かった。
頑張ってテニスをやっていた程度の里穂と、プロ選手を目指して英才教育を受けて来た由加理では、力量に雲
泥の差がある。由加理がその気になれば、あっと言う間に勝負はついてしまうだろう。しかし、それによって
里穂が素っ裸にされ、男たちの見世物にされるのは、由加理には耐え難かった。
(やっぱり、ダメ…)
由香理がイヤイヤするように頭を振った。里穂が、お尻が剥き出しになるのも構わず必死で打ち込んだボー
ルを返したレシーブは、由加理の狙いどおりコースを外れ、「フォルト」という審判のジャッジが響いた。
ルを返したレシーブは、由加理の狙いどおりコースを外れ、「フォルト」という審判のジャッジが響いた。
観客席の前に立ち、挑むような表情でアンスコを脱ぎ捨てた由加理がコートに戻ろうとすると、球拾いをし
ていた美奈が近づいてきた。
ていた美奈が近づいてきた。
「試合は、ちゃんとやった方がいいわよ…」
目を伏せたまま、独り言のようにそう言った美奈を、怒りに燃える目で睨みつけると、「あんたには関係な
いでしょ!」と吐き捨てるように言い返した。
いでしょ!」と吐き捨てるように言い返した。
(反愛国者で、淫乱で、意地悪のうえに、負け犬のくせに…)
かつての憧れの対象に対するイメージダウンは、ここに来てさらに大きくなっている。これまで、美奈が館
の手先となって転入生を虐めていると思い込んでいた由加理だったが、それでも、圧倒的な強さとオーラを見
せていた美奈にはどこかで畏怖の念を持っていた。しかし、コーチたちとの勝負に惨敗して以来、美奈は人が
変わったように、すっかり元気をなくしてしまったのだ。今では、練習もまともにすることがなく、キャプテ
ンとしての役割も放棄し、井上千春がその代行をしている。勝気な由加理にとって、今や美奈は軽蔑の対象で
しかなかった。
の手先となって転入生を虐めていると思い込んでいた由加理だったが、それでも、圧倒的な強さとオーラを見
せていた美奈にはどこかで畏怖の念を持っていた。しかし、コーチたちとの勝負に惨敗して以来、美奈は人が
変わったように、すっかり元気をなくしてしまったのだ。今では、練習もまともにすることがなく、キャプテ
ンとしての役割も放棄し、井上千春がその代行をしている。勝気な由加理にとって、今や美奈は軽蔑の対象で
しかなかった。
コートに入った由加理が、次のサーブに備えて構えようとすると、「タイム!」という声が聞こえて、里穂
が駆け寄って来た。その顔には険しい表情が浮かんでいる。
が駆け寄って来た。その顔には険しい表情が浮かんでいる。
「どういうつもり?!」
これまでに聞いたことのない、怒りに震える声が由加理を驚かせた。
「えっ…、里穂…、怒ってるの?」
「当たり前でしょ、手加減なんかして欲しくないわ!」
それは、お互いの気持ちが十分にわかり合っているからこその怒りだった。出会ってからまだ二週間しか経
っていないが、年頃の女の子にとって死ぬよりも辛い、地獄のような毎日を励まし合いながら耐えている絆
は、すでに十分に強かった。里穂の思いがわかり、由加理は思わず俯いた。
っていないが、年頃の女の子にとって死ぬよりも辛い、地獄のような毎日を励まし合いながら耐えている絆
は、すでに十分に強かった。里穂の思いがわかり、由加理は思わず俯いた。
「失礼じゃない!私に対しても、テニスに対しても!」
目に涙をためてそう言った里穂の目を見て、由加理も涙目で頷いた。
「うん…、ごめん…」
二人がコートの両サイドに分かれ、試合が再開した。思い切りスマッシュを打とうとする由加理の脳裏に、
さっきの美奈の声が響いた。
さっきの美奈の声が響いた。
「第1試合、菱田由加理選手の勝ち!」
本気を出した由加理の前に、里穂はひとたまりもなくポイントを連取され、観客の前でウエアを脱ぎ、続い
てスコートを脱いだ。全身をピンクに染め、恥ずかしさに震えながらも、全裸になったその姿はどこか誇らし
げに見えた。
てスコートを脱いだ。全身をピンクに染め、恥ずかしさに震えながらも、全裸になったその姿はどこか誇らし
げに見えた。
観客席の一部で大きなどよめきが起きた。美奈をずっと目で追いかけていた前田は慌てて自分の席を離れ、
どよめきの中心に駆け寄った。観客に囲まれたスタンド席の一つに美奈が腰を下ろしている。
どよめきの中心に駆け寄った。観客に囲まれたスタンド席の一つに美奈が腰を下ろしている。
驚いた表情で見つめる男たちの前で美奈は大きく脚を開いた。アンスコは履いておらず、めくれ上がったス
カートの裾からつるつるに剃り上げられた女陰が露わになった。
カートの裾からつるつるに剃り上げられた女陰が露わになった。
「どなたか、これを…」
そう言うと、美奈は籠に入れたテニスボールを一つ手に取って、男たちの前に差し出した。
「私の…、オ××コに入れてください…」
男たちがお互いに顔を見合わせた。美奈の名声を知っている者はもちろん、彼女のことを知らなくても、他
の部員と比較して群を抜く美少女であることは、見ただけで明らかだ。そんな美少女が股間を露わにし、正気
とは思えない願いを口にしている。どう反応したものか、さすがの男たちも戸惑っているのだ。
の部員と比較して群を抜く美少女であることは、見ただけで明らかだ。そんな美少女が股間を露わにし、正気
とは思えない願いを口にしている。どう反応したものか、さすがの男たちも戸惑っているのだ。
「お願いです…」
潤んだような目で哀願する美奈を見て、前田が高く手を挙げた。
「俺が…、俺が、入れてあげるよ…」
先を越された残念さを表情に浮かべた男たちが、左右に分かれて通り道を作り、美奈の前に進んだ前田が膝
をついた。
をついた。
無毛の大陰唇はそれほど大きくなかったが、縦長の柔らかな膨らみを見せている。割れ目がわずかに開い
て、ピンク色の肉ビラがわずかに顔をのぞかせていた。
て、ピンク色の肉ビラがわずかに顔をのぞかせていた。
彼にとって憧れの的であり、最高のアイドル有岡美奈の性器、他人が見ることなど想像さえできなかった女
の秘所が今、目の前にある。前田の頬が火照り、心臓が大きく高鳴った。股間に熱が籠り、痛いほど膨らんで
いるのがわかる。
の秘所が今、目の前にある。前田の頬が火照り、心臓が大きく高鳴った。股間に熱が籠り、痛いほど膨らんで
いるのがわかる。
「…、お願いします…」
囁くような声でそう言うと、美奈はほっそりした指を自ら股間に這わせ、肉の割れ目に指を掛けた。舟形の
膨らみをゆっくり押し開いていく。きれいなピンク色の粘膜が露わになる。
膨らみをゆっくり押し開いていく。きれいなピンク色の粘膜が露わになる。
「少し、濡らしてください…」
美奈はそう言うと、自らも包皮の上から敏感な芽をしごき始めた。前田が指を一本、温かい媚肉の中の挿入
し、抜き差しした。
し、抜き差しした。
「…あ、あぁ…」
美奈の身体がビクンビクンと跳ねた。前田は指を二本にして美奈の蜜壷をこねまわす。指の動きを早くする
と、クチャックチャッと音が聞こえてきた。
と、クチャックチャッと音が聞こえてきた。
「…舐めても、いいかな…?入れやすいように…」
「はい…」
前田は陰部に顔を近づけ、指先で割れ目を開いた。溜まっていた淫蜜が零れ落ちる。それを舌で掬い取りな
がら、美しいピンク色をした襞肉を一枚一枚舐めていった。
がら、美しいピンク色をした襞肉を一枚一枚舐めていった。
「あっ…、ああっ、あぁぁ…」
クリトリスの皮を剥いて唇で挟み、ザラザラの舌で舐め上げると、美奈は身悶えしながら、腰をせり上げ
た。膣に入れた指が強く締め付けられる。
た。膣に入れた指が強く締め付けられる。
「そろそろ…、ボールを入れて…」
美奈が喘ぎ声とともに、そう言った。前田は右手に持ったテニスボールを押し当ててみる。左手の指先で膣
口を開いてみたが、ボールの方が二回りほど大きそうだ。
口を開いてみたが、ボールの方が二回りほど大きそうだ。
(さすがに、これは入らないんじゃないか…)
そう思いながら指先に力を入れていくと、膣口の粘膜が薄く引き伸ばされ、ボールが3分の1ほどめり込ん
だ。
だ。
「すげぇ…」
横で覗き込んでいた隊員の感嘆の声が聞こえる。女の子の性器というのはかなり伸縮するのだなと、前田は
改めてそう思った。
改めてそう思った。
「もう少しだ…」
そう呟きながら、グイッと力を込める。
「あうっ…」という美奈の呻き声とともに、ふいに右手の抵抗がなくなり、テニスボールが完全に膣内に収ま
った。
った。
「ありがとうございます…」
脚を閉じ、立ち上がった美奈が前田に向かってお辞儀をした。ちょうどその時、審判の玉田の声が響いた。
「ボールガール!」
「はいっ!」
大きな声で返事をして、美奈が彼の傍に駆け寄って行く。その後ろ姿を見送りながら、前田は、なんとなく
満たされた気分を味わっていた。
満たされた気分を味わっていた。
「ボールガールは3年生の有岡美奈です。かつてはテニス界のプリンセスと呼ばれた彼女ですが、テロリスト
組織と通じていたことが発覚し、更生のために当館に送られたことは、多くのみなさんがご存知のことだと思
います。しかし、慰安嬢は彼女の淫らな性格にぴったりだったらしく、最近はテニスよりも、お客様の慰安の
方が楽しくなってしまったようです。そのせいで、テニスの練習もおろそかになり、今では球拾いぐらいしか
役に立たなくなってしまいました」
組織と通じていたことが発覚し、更生のために当館に送られたことは、多くのみなさんがご存知のことだと思
います。しかし、慰安嬢は彼女の淫らな性格にぴったりだったらしく、最近はテニスよりも、お客様の慰安の
方が楽しくなってしまったようです。そのせいで、テニスの練習もおろそかになり、今では球拾いぐらいしか
役に立たなくなってしまいました」
嘲笑交じりに晴亜がアナウンスする声を聞きながら、審判台の隣に立った美奈は肩幅に脚を開き、和式トイ
レで排泄する時のようにしゃがんだ。審判台から降りて来た玉田が、その股間に手を伸ばす。
レで排泄する時のようにしゃがんだ。審判台から降りて来た玉田が、その股間に手を伸ばす。
「ううっ…」
力みとともに、膣に入れたボールが玉田の掌に落ちた。
「ふふふ、このボール、ちょっと濡れすぎですよ」
玉田が聞こえよがしにそう言った。
「さあ、美奈、次のボールをオ××コに入れてもらってきなさい」
「…はい」
玉田の命令に返事をした美奈の目はどんよりと曇ったようになり、まるで別人のようだ。恵聖学園からの後
輩で、美奈を心から尊敬している長畑明穂が次の対戦のためにコートにおり、何度か声を掛けようとしたが、
あまりの彼女の変わりようが怖くなり、結局、最後まで声を掛けることができなかった。
輩で、美奈を心から尊敬している長畑明穂が次の対戦のためにコートにおり、何度か声を掛けようとしたが、
あまりの彼女の変わりようが怖くなり、結局、最後まで声を掛けることができなかった。
そして、全試合が終了した。
「紅組の勝利です。紅組を応援されたみなさんは、コートにおいでください」
晴亜のアナウンスが響き、朋美の案内で隊員たちがコートに下りて来た。
白組の選手たちは、試合に負けて全裸になっている者だけでなく、試合には勝った者も着ているものをすべ
て脱いだ。
て脱いだ。
コートに跪いた鳥居仁美の周りを数人の隊員が取り囲んだ。小便をする時のようにズボンのチャックを開
き、一斉に肉棒を突き出す男たちの真ん中で、仁美は差し出されたペニスを舐め始めた。性欲処理にはフェラ
抜きが一番簡単とあって、コートのあちこちで、全裸の少女を取り囲んだ男たちの輪が出来上がっていく。
き、一斉に肉棒を突き出す男たちの真ん中で、仁美は差し出されたペニスを舐め始めた。性欲処理にはフェラ
抜きが一番簡単とあって、コートのあちこちで、全裸の少女を取り囲んだ男たちの輪が出来上がっていく。
クチュッ、クチュッ…と、唾液を絡める卑猥な音が響く。
正面に立った男の肉棒を口に咥えた仁美は、顔を捻り、絞める角度を変えながら、何度も唇を根元からカリ
までの間を往復させている。その間も左右の手は、それぞれ別の男の怒張を握って、器用な手つきで扱いてい
た。
までの間を往復させている。その間も左右の手は、それぞれ別の男の怒張を握って、器用な手つきで扱いてい
た。
「で…でるっ…」
我慢の限界に達した男が射精し、精液が喉の奥にほとばしる。
「…ウッ、ムッ、ムグゥ…」
仁美は口中に出された精液を飲み込み、尿道に残った精液まで余すところなく吸い取った。
「ほらほら、今度はこっちだよ…」
右手の男が焦れたように催促した。彼の方を向き直ると、怒張に手を握ったまま、仁美は先端を舌で舐め
た。
た。
「うっ…」
ひと舐めされただけで背筋に電流が走るような快感を感じ、隊員がブルッと身体を震わせる。仁美は怒張に
押しつけるようにして舌を這わせ、裏の皺に沿って舌先で舐め上げた。カリの裏側を舌先で突くようにしたか
と思うと、玉袋を口に含んで舌で転がす。男の急所を知り尽くしたフェラチオに隊員は悶絶し、彼女の唾液と
先走り液に塗れた肉棒は限界まで膨れ上がった。
押しつけるようにして舌を這わせ、裏の皺に沿って舌先で舐め上げた。カリの裏側を舌先で突くようにしたか
と思うと、玉袋を口に含んで舌で転がす。男の急所を知り尽くしたフェラチオに隊員は悶絶し、彼女の唾液と
先走り液に塗れた肉棒は限界まで膨れ上がった。
真面目で研究熱心…、誰からもそう評される仁美のアドバイスを信頼し、冴子は常に耳を傾けた。「脱出で
きる日のために、この館で生き抜く」という冴子の決意を聞かされてからは、慰安のための卑猥なテクニック
も率先して研究し、積極的に身に着けることで、彼女をサポートしようとしてきたのだ。仁美はいつでも仁美
らしく、変わることがなかった。
きる日のために、この館で生き抜く」という冴子の決意を聞かされてからは、慰安のための卑猥なテクニック
も率先して研究し、積極的に身に着けることで、彼女をサポートしようとしてきたのだ。仁美はいつでも仁美
らしく、変わることがなかった。
「気持ちいいですか…?」
柔らかな笑顔とともに上目遣いで尋ねられた瞬間、隊員は我慢できなくなり、仁美の顔めがけて勢い良く精
液を放った。
液を放った。
フェラチオでは飽き足らない隊員たちは、屋外であることもお構いなしに、女生徒たちとのセックスを求め
た。
た。
清水香奈枝は手のひらと膝を地面について、四つん這いになった。あっと言う間に、その周りに人垣ができ
る。恵聖学園から美奈と一緒に連れて来られた彼女は、テニスの力量はともかく、その美しさ、可愛らしさで
は美奈をすら上回る。慰安嬢としての香奈枝の人気は高く、今では彼女を常に指名する常連が何人もできてい
た。
る。恵聖学園から美奈と一緒に連れて来られた彼女は、テニスの力量はともかく、その美しさ、可愛らしさで
は美奈をすら上回る。慰安嬢としての香奈枝の人気は高く、今では彼女を常に指名する常連が何人もできてい
た。
香奈枝が膝を伸ばし、お尻をゆっくり上げて行く。ゆで卵のような染み一つないきれいなお尻が、クネクネ
と動きながら、隊員たちの前に差し出された。丸みを帯びた臀部の間にセピア色のグラデーションを引いた菊
座が見え、つるつるに剃り上げられたふっくらした大陰唇が縦に口を閉じている。
と動きながら、隊員たちの前に差し出された。丸みを帯びた臀部の間にセピア色のグラデーションを引いた菊
座が見え、つるつるに剃り上げられたふっくらした大陰唇が縦に口を閉じている。
「私の…オ××コに…、オ×ン×ンを…入れてみてください…」
香奈枝は可愛い声をしており、その声で淫らなお願いを口にすると、ゾクゾクするほど官能的だ。隊員たち
は一瞬、お互いの顔を見合わせたが、もとよりその気で集まっている者ばかりである。すぐに、なんとなく順
番が決まった。
は一瞬、お互いの顔を見合わせたが、もとよりその気で集まっている者ばかりである。すぐに、なんとなく順
番が決まった。
最初の男が香奈枝の双臀を鷲づかみにして左右に広げ、亀頭をあてがう。差し出された香奈枝の秘孔に肉棒
が吸い込まれていく。
が吸い込まれていく。
「あうっ、ああぁん…」
香奈枝の口から、甘い喘ぎ声が漏れた。その声が男の興奮を一気に高めた。香奈枝の腰を掴み、男は怒張の
抜き差しを始める。男の下腹が香奈枝のヒップを打つ音がバコッ、バコッとコートに響く。
抜き差しを始める。男の下腹が香奈枝のヒップを打つ音がバコッ、バコッとコートに響く。
「うっ、…うっ…」
男の動きにあわせて、薄く開いた香奈枝の唇からくぐもった声が漏れ出した。男は香奈枝の滑らかな背中を
抱きしめるようにしてバストに手回し、無我夢中で乳房を揉みしだく。
抱きしめるようにしてバストに手回し、無我夢中で乳房を揉みしだく。
「あうっ、あうっ…あうっ…」
怒張が香奈枝の子宮の奥深くまで入り込み、抜き差しの速度を早めていく。香奈枝が腰を激しく振って、し
きりに喘ぎ声をあげる。
きりに喘ぎ声をあげる。
「…ううっ、う…いっ…」
膣が収縮し、男の怒張を絞り上げた。キュッ、キュウー、キュッと強く弱く締め上げる。
「でっ、でるよ。…でるよ」
切羽詰まった男の声とともに、香奈枝の中で熱いものが爆ぜた。ヒダ肉に絡み付くように、ヌルヌルの汚濁
が飛び散る。
が飛び散る。
「あぁ、ああぁ、あぁぁぁぁっ…」
香奈枝が足の指先までツッパリ、背中を仰け反らせて、絶頂の声を上げた。
男が怒張を抜くと、精液と愛液が交じり合った白濁が香奈枝の秘孔からタラリと地面に零れ落ちる。魏国派
遣部隊の隊員たちは、生命の危険と引き換えに、一泊二日の館での滞在中、中出しの許可を受けているのだ。
遣部隊の隊員たちは、生命の危険と引き換えに、一泊二日の館での滞在中、中出しの許可を受けているのだ。
審判台の横に作られた放送席から立ちあがった晴亜が、球拾いをしている美奈を呼び寄せた。
「有岡さんも、隊員のみなさんとセックスしたいわよね…」
邪悪な笑顔で晴亜が尋ねる。
「…はい」
玉田に返事をした時と同じように、美奈が人形のような表情で答えた。
「ふふふ…、いやらしい子ね。じゃあ、思う存分、セックスしていらっしゃい」
晴亜に背中を押された美奈が、ウエアを脱いでコートに入って来たのを見て、多くの隊員たちが群がってき
た。彫刻のように美しい裸身は、見ているだけでも飽きることがない。テニスに興味がない者でも、テニス界
のプリンセスの名は国民に知れ渡っている。
た。彫刻のように美しい裸身は、見ているだけでも飽きることがない。テニスに興味がない者でも、テニス界
のプリンセスの名は国民に知れ渡っている。
四つん這いになった美奈の口元に、勃起した陰茎を差し出された。美奈は、ほぼ条件反射のように舌を出
し、亀頭をペロペロと舐め始めた。唾液をまぶされた怒張がどんどん反り返って行く。
し、亀頭をペロペロと舐め始めた。唾液をまぶされた怒張がどんどん反り返って行く。
「ううっ、気持ちいいっ…」
男が上ずった声をあげた。美奈は怒張を咥え、根元からカリまで、唇で絞めたり緩めたりしながら吸ってい
く。
く。
「すごい上手い…、たまらない…」
目を閉じてそう言うと、男は瞬殺で射精して果てた。
背後に立つ気配を感じて、美奈はお尻を高く上げた。桃のようなヒップがゆっくりと上がって、男に差し出
される。とたんに怒張が美奈の秘孔を突いてくる。膣口に滑り込んだ先端が体内に侵入して来た。美奈は自ら
腰を振って、肉棒を身体の奥まで迎え入れる。
される。とたんに怒張が美奈の秘孔を突いてくる。膣口に滑り込んだ先端が体内に侵入して来た。美奈は自ら
腰を振って、肉棒を身体の奥まで迎え入れる。
「む…、むぐぐぅ…」
男の精液を飲み終わると、次の男が美奈の頭を押さえ、口に挿入する。美奈は当然のことのように、頬をへ
こませて肉棒を擦り、唇に咥えて吸い上げる。気が付けば、口も性器も、すでに五人目の男を迎えていた。こ
うして、美奈は前から後ろから、上下の口で次々に男の性欲を処理していくのだ。
こませて肉棒を擦り、唇に咥えて吸い上げる。気が付けば、口も性器も、すでに五人目の男を迎えていた。こ
うして、美奈は前から後ろから、上下の口で次々に男の性欲を処理していくのだ。
「あれ、本当に有岡美奈、だよな…」
そう呟く隊員の声が聞こえた。
「そのはずなんだけど…、なんだかなぁ…」
淫らな肉人形のような美奈の様子に幻滅した男たちもいるようだ。彼女を囲んでいた隊員たちは少しずつ数
が減り、他の少女たちの所に移って行った。
が減り、他の少女たちの所に移って行った。
それでも、美奈の身体を弄ぶ男の列は途切れることはない。
フェラチオをさせている男が手を伸ばし、充血してサーモンピンクの色を濃くした美奈の乳首を揉みしごい
た。指先でこねくり、押し潰しては引っ張る。
た。指先でこねくり、押し潰しては引っ張る。
それと調子を合わせるように、バックで繋がっている男の指がクリトリスを捕えた。ピストン運動をしなが
ら、指先でクリトリスを刺激する。
ら、指先でクリトリスを刺激する。
「い、いいっ…あああああ、そこ、たまらない…」
美奈が狂ったようによがり声をあげる。その声を聞きながら、二人の男たちは、それぞれ口と膣で同時に果
て、美奈の体内に射精した。
て、美奈の体内に射精した。
「いい、い、イク、イク、イ、クゥ…」
美奈が全身を震わせて、絶頂を告げた。慰安嬢のセックスは常に本気、男をいかせる時は必ず自分もイクの
が、館の作法だ。
が、館の作法だ。
「さすが有岡さんね。慰安嬢になるために生まれて来たみたいだわ…」
そう言って嘲笑する晴亜の声が、美奈の耳にはどこか遠くから聞こえてくる呪いのように響いた。
練習から夕食までの限られた時間、テニス部の主だったメンバーはコーチたちの目を盗んで集まり、相談を
していた。場所は物品倉庫。朋美を守るために館のスタッフとなった岩崎良宏が管理を任されているため、館
の目が唯一届かない場所だ。
していた。場所は物品倉庫。朋美を守るために館のスタッフとなった岩崎良宏が管理を任されているため、館
の目が唯一届かない場所だ。
体力が有り余った若い隊員たちの性欲処理を、たっぷり時間いっぱいまでさせられた白組の部員たちは、さ
すがにぐったりしている。
すがにぐったりしている。
「有岡さんは必ずもとどおり、元気になりはるわ」
柔らかなイントネーションで、しかし確信を込めて口火を切ったのは、千春だった。
「有岡さんがやろうとしていたことは、館のどこかに監禁されているはずの、日比谷先生を探すことでしたよ
ね。まず、それからやりましょう」
ね。まず、それからやりましょう」
集まったみんなを見渡し、そう声をかけたのは、小倉恭子だった。恵聖学園の中でテニスの技量は美奈に次
ぐと言われた恭子は、同時に精神面で弱さが指摘されることが多かった。しかし、館での苦難を乗り越える中
で確実に強くなっている。もし、元の生活に戻れたら、彼女はキャプテンとなってみんなを引っ張り、テニス
の選手としても成功することだろう。
ぐと言われた恭子は、同時に精神面で弱さが指摘されることが多かった。しかし、館での苦難を乗り越える中
で確実に強くなっている。もし、元の生活に戻れたら、彼女はキャプテンとなってみんなを引っ張り、テニス
の選手としても成功することだろう。
恭子の視線に応えて、仁美が力強く頷く。参謀役だった那珂冴子がいなくなり、リーダーの美奈の心が折れ
てしまった今こそ、残されたメンバーが力を発揮する時だ。
てしまった今こそ、残されたメンバーが力を発揮する時だ。
幸い、理事選挙に気をとられている松川は、ここのところ部員たちをほとんど管理しておらず、代役をつと
めているコーチたちの関心事は部員を虐めることであって、そもそもテニス部の運営や館の体制には全く興味
がない。一方で、もともと松川がテニス部に全責任を負う体制になっていたため、館の直接の管理運営も彼女
たちには及ばなくなっていた。自由に行動するなら、むしろ今が絶好のチャンスなのかもしれない。
めているコーチたちの関心事は部員を虐めることであって、そもそもテニス部の運営や館の体制には全く興味
がない。一方で、もともと松川がテニス部に全責任を負う体制になっていたため、館の直接の管理運営も彼女
たちには及ばなくなっていた。自由に行動するなら、むしろ今が絶好のチャンスなのかもしれない。
話し合いの結果、まず、日比谷と接触した生徒がいないかどうかを調べてみようということになった。部員た
ちも分担して体育科の生徒たちを中心に当たることにしたが、普通科も含めた生徒全員から情報を集めるとす
ると、生徒会長の森川亜弓に協力を仰ぐのが一番だ。美奈がいないので、朋美が亜弓に相談することも決め
た。
ちも分担して体育科の生徒たちを中心に当たることにしたが、普通科も含めた生徒全員から情報を集めるとす
ると、生徒会長の森川亜弓に協力を仰ぐのが一番だ。美奈がいないので、朋美が亜弓に相談することも決め
た。
「話は変わるんですけど、私、一つ気になっていることがあるんです…」
そう言ったのは、明穂だった。少女たちの視線が、彼女に集まる。
「有岡さん、このところ、自分の部屋に戻っていないようなんです…」
他の部員たちに聞いても、美奈の姿を寮で見かけた者はいなかった。考えてみれば、「プライベートレッス
ン」を掛けたコーチとの試合以降、こうした秘密の相談の場に来ることができないだけでなく、練習の時でさ
え、美奈と他の部員たちとの接点が断たれている。部員たちの間に急に不安が広がった。
ン」を掛けたコーチとの試合以降、こうした秘密の相談の場に来ることができないだけでなく、練習の時でさ
え、美奈と他の部員たちとの接点が断たれている。部員たちの間に急に不安が広がった。
派遣部隊の出迎えアトラクションの後、休憩どころか、シャワーを浴びることも、着替える間さえもなく、
美奈はコーチ室に戻って来た。コーチとの練習試合に負けたことで始まった「プライベートレッスン」は1日
で終わるものではなく、今もずっと続いているのだ。
美奈はコーチ室に戻って来た。コーチとの練習試合に負けたことで始まった「プライベートレッスン」は1日
で終わるものではなく、今もずっと続いているのだ。
床の上に横たわった曽根の胸に両手をおき、その巨根と騎乗位でつながった美奈は、自ら激しく腰を振って
いた。
いた。
「ああっ、いい…、いっ、いいの…、曽根様、もっと突き上げて…」
「なんだ、美奈、すっかりメス犬になってしまったな」
自分からおねだりしている美奈に嘲笑を浴びせながら、曽根は波打って揺れる美奈の乳房を鷲掴みにし、腰
を激しく突き上げた。
を激しく突き上げた。
「あん、あ、ああん…いい、いいっ」
美奈は、白い喉を仰け反らせ喘ぎ声を上げる。
「感じるんだろ?どんどん締め付けが強くなってくるぞ」
「はい…、感じてます…。オッパイも、オ××コも、すごく感じてます…」
美奈は、細腰をくねらせ喘ぎ声をあげた。
「プライベートレッスン」の間、美奈は寮の部屋に帰ることは許されず、授業や練習、慰安スケジュールを
こなしている時以外は、すべてコーチ室で過ごしている。睡眠を取るのもこの部屋だし、排泄もトイレではな
く、ここに置いてあるバケツでさせられた。しかも、昼夜を問わず、コーチたちの気の向くままに身体を弄ば
れるのだ。
こなしている時以外は、すべてコーチ室で過ごしている。睡眠を取るのもこの部屋だし、排泄もトイレではな
く、ここに置いてあるバケツでさせられた。しかも、昼夜を問わず、コーチたちの気の向くままに身体を弄ば
れるのだ。
「ああ、いいっ、いい…、曽根様、ど、どうぞ一緒にイってください」
美奈のおねだりに、曽根は怒張にみなぎった力を解放した。
「いい、いい…、イッ、イク、イクウウウ…」
秘孔を満たしていく性感に、美奈はその白い喉を反り返らせピクピクと肢体を痙攣させた。
テニスの技術が目に見えて落ちていることでアイデンティティを傷つけられ、それでなくても精神的にまい
っている美奈は、コーチたちとともに半監禁状態に置かれることで、気力、体力ともに限界まで追い込まれて
いる。それが、晴亜たちが企図した「プリンセスの死」の正体だった。
っている美奈は、コーチたちとともに半監禁状態に置かれることで、気力、体力ともに限界まで追い込まれて
いる。それが、晴亜たちが企図した「プリンセスの死」の正体だった。
曽根は、全裸のまま床でぐったりしている美奈の両手を皮製の手錠で固定すると、天井から滑車を介して吊
るされているロープの先の金具に固定した。
るされているロープの先の金具に固定した。
「準備OKだ、吊り上げていいぞ」
合図を受けて玉田が壁のハンドルを回し、美奈を吊り上げて行く。ロープの高さを調整すると、美奈の身体
は、爪先が地面にやっと付くぐらいにまで吊り上げられてしまった。曽根はさらにロープを使って彼女の裸体
を縛っていく。乳房が縄で円錐型にきつく絞り出され、両脚を大きくM字に開いた格好で、膝にかけたロープ
が天井から吊るされた金具に括り付けられる。
は、爪先が地面にやっと付くぐらいにまで吊り上げられてしまった。曽根はさらにロープを使って彼女の裸体
を縛っていく。乳房が縄で円錐型にきつく絞り出され、両脚を大きくM字に開いた格好で、膝にかけたロープ
が天井から吊るされた金具に括り付けられる。
「見ろよ、いい眺めだぜ…」
曽根が満足げに言った。晴亜が上機嫌で笑い声を立て、玉田がニヤニヤ笑って、露わになった美奈の股間を
覗き込む。剥き出しになった美奈の性器は、ちょうど彼の目の前にあった。
覗き込む。剥き出しになった美奈の性器は、ちょうど彼の目の前にあった。
「今日は、これを試してみようかしら」
そう言って晴亜が持ってきたのは、DIYで使う電動ドリルだった。屋外でログハウスなどを組み立てるた
めの本格的なもので、ずっしりと持ち重りがする。晴亜は先端を美奈に向けると、おどけたポーズでマシンガ
ンのように構えて見せる。
めの本格的なもので、ずっしりと持ち重りがする。晴亜は先端を美奈に向けると、おどけたポーズでマシンガ
ンのように構えて見せる。
「先につけるのは、これね」
玉田がオネエ口調で言いながら、肌色をした極太の疑似男根を取り出した。ドリル先端のドライバーにはめ
込むように取りつけると、晴亜がスイッチを入れる。いかにも工具といったヴィーン…というモーター音が室
内に響き、先端に取りつけられた疑似男根が猛烈な勢いで回転し始めた。
込むように取りつけると、晴亜がスイッチを入れる。いかにも工具といったヴィーン…というモーター音が室
内に響き、先端に取りつけられた疑似男根が猛烈な勢いで回転し始めた。
「ふふっ、いいわねぇ…」
晴亜がニヤッと笑い、曽根が拍手をする。ブーンッと唸る音を響かせて、晴亜が手にしたドリルバイブが美
奈に近づいてくる。
奈に近づいてくる。
「だっ、…だめ…、そんな…」
美奈の顔が恐怖でひきつった。高速で回転するドリル、先端に取りつけられたバイブは一般的な男根の倍ぐ
らい太さがある。それはもはや大人の玩具、淫具というよりは、凶器と言って良かった。
らい太さがある。それはもはや大人の玩具、淫具というよりは、凶器と言って良かった。
「いやぁ、そんなの…入れないでっ!」
美奈が宙吊りになった身体をよじる。晴亜がバイブの先端を秘孔にあてがった。
「だめ、やっ、やめて…」
「何を言ってるの。これもプライベートレッスンの一つよ!」
そう言いながら、晴亜がグイッと力を入れると、バイブのカリの部分が回転しながら美奈の割れ目に入って
いく。
いく。
「ああっ!」
美奈が子を上げ、ロープに吊られた身体が揺れる。晴亜がバイブをさらに押し込んだ。ブシュッという音を
発て、美奈の秘孔がバイブを飲み込んだ。
発て、美奈の秘孔がバイブを飲み込んだ。
「うっ、い…や…あっ…」
美奈は顎を仰け反らし、うめき声をあげた。腰をくねらせる動きで、宙吊りになった身体がブランコのよう
に揺れる。
に揺れる。
「…ぬっ、抜いてっ!だっ、だめ…」
その腰が円を描いてうねり、蜜壷はおぞましいドリルバイブをさらに飲み込む。中に溜まっていた淫蜜が溢
れだし、地面に滴り落ちる。
れだし、地面に滴り落ちる。
「いいっ、…いっ」
美奈の呼吸がさらに荒くなってきた。胸に、お腹に汗が浮き、蛍光灯を反射して輝いている。
「あはっ、ああ、あはぁ…」
顔を左右に振ると汗を掻いた頬に髪の毛が貼りつき、さらに色っぽさを増していく。数本の髪の毛が唇の端
に貼りつく。玉田はギラギラした目で、宙吊りでうねる美奈の身体を凝視していた。
に貼りつく。玉田はギラギラした目で、宙吊りでうねる美奈の身体を凝視していた。
「胸も触ってやったら」
「こうか?」
晴亜に促された曽根がきつく縄で絞り出された美奈の双乳を鷲掴みにする。乳首がこれでもかと尖りだし
て、天を向いている。曽根は胸を力任せに揉み、自慢げに玉田たちに見せた。双乳が、曽根の手で淫らに形を
変えていく。
て、天を向いている。曽根は胸を力任せに揉み、自慢げに玉田たちに見せた。双乳が、曽根の手で淫らに形を
変えていく。
玉田が手を伸ばし、充血しきって膨らんだ乳首を指で弾く。
「くはぁっ…、だめぇ…」
美奈の身体が、ビクっと痙攣してのけ反り、宙吊りの裸体がブランコのように揺れた。
「ほらほら、抜けちゃったじゃない…」
電動ドリルを手にした晴亜がニヤニヤ笑いながら言った。曽根が美奈の腰を支え、あらためて先端の淫具を
美奈の膣内に挿入する。
美奈の膣内に挿入する。
「…だっ、だめぇ、もう…、だめです、許して…」
美奈がうわごとのように哀願するのも構わず。コーチたちは再び疑似男根を根元まで挿入した。
「い、いい…うっ」
「行くぞ、それっ!」
激しいモーター音とともに、再びドリルが回転し始めた。回転数が徐々に上がっていき、ついに最大出力の
スイッチが入った。
スイッチが入った。
「ぎゃあああっ、ああっ!」
美奈が叫び声をあげ、身体が電気を浴びたようにガクン、ガクンと揺れる。
晴亜が激しく回転するバイブを抜き刺しする。グチャ、グチャと美奈の愛蜜が白い泡を立て、ポタポタと床に
滴り落ちる。
滴り落ちる。
「いやっ、壊れちゃうっ、オ××コ壊れちゃうーっ!」
美奈が悲鳴をあげた、バイブの抜き刺しに合わせて、腰を激しくくねらせ、全身を捩る。イヤイヤするよう
に左右に顔を振るたび、汗が飛び散った。
に左右に顔を振るたび、汗が飛び散った。
「いっ、いっ、き…そぉう…」
美奈のからだが、弾かれるように仰け反った。
「いっ、イ…ク…イクぅ…」
喘ぎ声とともに、太股がビクビクと痙攣したかと思うと、ドリルを挿入された女陰から水しぶきが噴き出し
た。
た。
「ははは、見て!潮を噴いてるわよっ!」
うれしそうに言いながら晴亜がドリルで膣口から抜くと、失禁したらしく股間からコートに向けて美奈の尿
が放物線を描く。
が放物線を描く。
「汚いわね、潮だけじゃなくて、お漏らしまでしてるの!」
晴亜が美奈を指さし、嘲笑の声をあげた。力の抜けた裸体がロープに吊られて揺れている。視線を伏せ、俯
いた美奈の頬を涙が伝い、ポタポタと地面に落ちた。
いた美奈の頬を涙が伝い、ポタポタと地面に落ちた。
「ううぅ…」
思わず嗚咽が込み上げてくる。こうなると、もはや悲嘆の波を押しとどめることができなくなり、美奈は子
どものように泣きじゃくった。どうして自分はこんなに弱く、脆くなってしまったのだろう…、「しっかりし
なさい」と心のどこか叫ぶ声がする。しかし、それは、すぐに混沌とした意識の中に沈み込んでしまった。
どものように泣きじゃくった。どうして自分はこんなに弱く、脆くなってしまったのだろう…、「しっかりし
なさい」と心のどこか叫ぶ声がする。しかし、それは、すぐに混沌とした意識の中に沈み込んでしまった。
松川は時計を見た。午後8時…、魏国派遣部隊の隊員たちは、今頃、指名した女生徒の部屋を訪問してセッ
クスを楽しんでいるだろう。ここまでくれば、普通科を含めて館全体で、通常の慰安コースに乗っていくだけ
だ。
クスを楽しんでいるだろう。ここまでくれば、普通科を含めて館全体で、通常の慰安コースに乗っていくだけ
だ。
練習試合の観戦も、その後の罰ゲームも好評のうちに終わったと報告を受けている。シャワーや入浴、夕食
の相手までをテニス部で担当したが、特にトラブルもなく、隊員たちを十分に楽しませたようだ。
の相手までをテニス部で担当したが、特にトラブルもなく、隊員たちを十分に楽しませたようだ。
責任を果たしたとの思いから、ホッと一息ついた時、松川の携帯電話が鳴った。表示を見ると、事務局長の
南原からだった。
南原からだった。
「もしもし…」
松川が画面をタップすると、南原の声が聞こえた。
「館長がお会いになります」
南原はいつものように、ごく簡潔にそう言った。
「そうですか!」
松川の顔に喜色が浮かんだ。
窓辺に立った諸藤は、さっきからじっと外の景色を眺めている。松川が入室を許されてから相当の時間が経
過するが、諸藤は振り返るどころか、彼に対して声一つかけることがなかった。
過するが、諸藤は振り返るどころか、彼に対して声一つかけることがなかった。
「トップ・プレイヤーとしての実力を維持させること…」
諸藤がポツリとそう言った。
「はっ…?」
諸藤の言葉がすぐには理解できず、松川は怪訝な顔で聞きなおした。
「君を雇用した時の条件は、テニス部員たちに練習はきちんとさせ、その実力を維持させることが、契約内容
だったと思うが…」
だったと思うが…」
振り返った諸藤は無表情のまま、松川の顔をじっと見た。
松川は内心、冷や汗をかいた。原田、玉田、曽根という3人のコーチたちの「練習」は、それ自体が見世物
であり、テニス少女たちを玩具にした凌辱でしかない。このまま続けさせれば、テニスの上達どころか、彼女
たちの選手生命を奪うことになるだろう。それがわかっていながら、松川は理事長選挙にかまけ、むしろ、面
白がってコーチたちに練習を任せて来た。それが館長の不興の原因だったとは、彼にとってあまりに意外であ
った。
であり、テニス少女たちを玩具にした凌辱でしかない。このまま続けさせれば、テニスの上達どころか、彼女
たちの選手生命を奪うことになるだろう。それがわかっていながら、松川は理事長選挙にかまけ、むしろ、面
白がってコーチたちに練習を任せて来た。それが館長の不興の原因だったとは、彼にとってあまりに意外であ
った。
「君は、それを守っているか?」
諸藤の声から感情を汲み取ることは難しいが、松川を責めていることだけは確かだ。この館を作り、その頂
点にいる男は、慰安嬢など所詮は使い捨ての玩具に過ぎないと思っている松川たちとは、根本から考え方が違
うらしい。
点にいる男は、慰安嬢など所詮は使い捨ての玩具に過ぎないと思っている松川たちとは、根本から考え方が違
うらしい。
「…承知しております…」
「その言葉、確かだね。テニス部員たちの技量を引上げこそすれ、落とすことのないようにしてくれるのだ
ね」
ね」
諸藤が低い声で念を押した。今や、防衛隊の幹部でさえ震え上がらせると言われる迫力に、松川は反射的に
直立不動した。
直立不動した。
「はいっ!」
「では、君の要求を聞くことにしよう」
そう言うと、諸藤はやっと椅子に腰かけ、組んだ手の上に顎を乗せた。
|
|