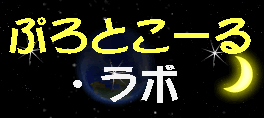マッチョな身体に似合わない、玉田の甲高い声がコートに響いた。
観客スタンドには、今日もテニス連盟の役員たちが最前列に陣取っている。先日の常任理事会以来、理事た
ちが数人ずつ、日替わりで館にやってくるような有様だ。
「当テニス部では、先輩が後輩を指導することを重視しています。なにしろ、この有岡をはじめ、女子テニス
界で有数の実力を持っていた選手たちが揃っているわけですから…」
さりげなく「持っていた」と過去形にした玉田の言葉が美奈の心に引っ掛かり、思わず顔が強張る。その声
のニュアンスから、玉田が彼女を傷つけるために、わざと言っているということが伝わってくる。「ムダな練
習を重ねているうちに、テニスの実力は徐々に落ちていく」「お前たちは、もはやテニス選手ですらなく、男
の玩具なのだ」、言外にそんな毒が含まれていた。
「そうは言いながら、ここでのテニスの指導は、独自の理論にもとづいています。先輩部員に指導をさせる場
合は、コーチの指示を正確に伝えることが必要です。そこで…」
そう言いながら、玉田が取り出したのは、極太のバイブレーターだった。ペニスを模った太い紫色のグロテ
スクな形と色をして、砲身は三日月のように反り返り、クネクネと走る皺とブツブツとした突起がそこら中に
刻まれている。
「これは、リモコン式のバイブです」
そう説明する玉田の手には、テレビのリモコンを思わせる装置が握られていた。そこにはスイッチだけでな
く、多数のボタンやランプがついている。
玉田がリモコンのスイッチを入れて見せた。観客たちの耳に届くほどの大きさでブーンッと音をあげて、バ
イブが唸る。手元のリモコンを操作すると、何段階にも分けて強弱が変わるのはもちろんのこと、回転した
り、蛇のようにうねったり、間歇運動をしたり、様々な音と動きの変化を見せる。
「私たちコーチは、このリモコンを使ってキャプテンの有岡に指示を送るのです」
玉田はそう言うと、観客たちが詰め掛けたスタンドの前に美奈を呼び寄せた。
「よし、有岡、これをオ××コに入れなさい」
「はい…」
美奈は軽く唇を噛んでアンスコを膝までおろし、理事をはじめ多くの観客が見つめる前できれいに陰毛を剃
り上げた陰部を露わにした。指先で割れ目を軽く広げ、自らバイブの先端を秘孔にあてがう。
「おいおい、あんな太いの、入るのか…」
食い入るように見ていた男が心配そうな声をあげた。井筒という初老の男で、選手出身ではなく、事務方を
長年務めて連盟の理事になった経歴の持ち主だ。井筒の目に映る極太のバイブは、コーヒーのロング缶ほどの
太さがあるように見える。挿入すれば、美奈の小さな膣口が目いっぱい広がり、無理やり入れると裂けてしま
いそうだ。
「全く問題はありません、大丈夫です。何しろ、毎日数え切れないほどのチ×ポを入れて、しっかり鍛えてい
るオ××コですからね」
おどけた様子で玉田が言うと、スタンドのあちこちで、観客たちが卑猥な嘲笑を漏らした。美奈の頬にカッ
と血が上る。
「さあ、早く入れなさい」
玉田が挿入を促した。観客たちが見つめる中、美奈は軽く息を吐くと、ほっそりした指でグイッと押し込
む。バイブのカリの部分は難なく彼女の割れ目に入っていく。
「すごいな。あんな太いの、本当に呑み込むんだな」
井筒が感心したような声をあげた。美奈がバイブをさらに押し込み、根本まで挿入する。枝分かれした突起
が、ちょうどクリトリスに押し当てられ、思わず小さな喘ぎ声を漏らした。
「よし、これは後ろですよ」
膣に入っているものより少し細めのバイブを、玉田が美奈に手渡した。
美奈は右手でそれを受け取ると、観客たちに向かってお尻を突き出し、左手の指で割れ目を広げた。皺の刻
まれた窄まりが露わになる。本当は他人に見せたくない場所を、自ら曝け出さなくてはならない羞恥に、美奈
の耳が紅く染まっている。
「うっ…」
美奈は、自らの手でアヌスにバイブを宛がった。丸く加工された先端が、皺の刻まれた菊座を押し広げてい
く。
「おおっ!」
前後の肉穴が大きく円形に口を広げ、太い異物を挿入されている様子に、観客たちが思わず声をあげる。満
足げに頷いた玉田は、観客たちを見やりながら、手にしたリモコンのスイッチをいれた。
ウィーン、ウィーンと観客の耳にも届くほどの音を立てて、バイブがうねり始めた。それを合図に、美奈が
軽い呻き声とともに右手を上げ、右側に腰を捻った。
「今、バイブが有岡の中で、右側の膣壁を擦っています」
「次は左…」
美奈が左手をあげ、左に腰を捻る。玉田がさらにスイッチを切り替えていくと、美奈はそれに合わせて腰を
前後左右に揺する。
「あっ…あっ、あんっ!ううぅ…」
徐々に振動の強さが上げられていく。両穴を激しくかき回された美奈が喘ぎ声を漏らし、全身をビクビク震
わせて動きを止めると、ガクッとその場に蹲った。早くも、一度目の絶頂を迎えたようだ。
(ふふふ、いい気味ですね…)
心の中で、玉田がそう呟いた。美奈をマリオネットのように操りながら、彼は愉快でたまらなかった。
公式審判員の資格を持つ玉田は、数年前、あるジュニア女子の大会で審判を務めた。優勝決定戦まで進んだ
時、登場した選手を見て、彼は驚きを隠せなかった。世界で通用する力と、目を見張るほどの美少女ぶりで世
間の注目を集め始めたプレイヤー、有岡美奈だった。
まだ中学生だったが、間近で見る美奈は天使のように愛らしく、それでいて気の強そうな表情がとても魅力
的で、玉田はすっかり心を奪われた。
美奈が圧勝するだろうと誰もが思った試合。しかし、油断していたのか、体調が万全でなかったのか、格下
の選手を相手に美奈は終始押され気味だった。主審を務めながらも、公平に見ることができず、玉田はヒヤヒ
ヤしながら試合を見ていた。
試合後半、流れを覆すために、美奈が渾身のスマッシュを打つ。それは微妙なコースだったが、玉田はポイ
ントを認定した。美奈のファンになってしまった贔屓目に加えて、有名選手を勝たせておけば問題はないだろ
うという安易な判断があった。当然のことながら相手選手が猛烈に抗議をする。
スタープレイヤーの有岡美奈に恩を売っておこうという下心もあり、ミス・ジャッジを認めずに押し切ろう
としたその時、なんと美奈本人が、相手選手の抗議を認めるべきだと主張したのだ。
(余計なことを言いやがって…)
美奈のフェアプレー精神から出たものだったが、玉田は恥をかかされたと思い、心の奥に暗い恨みを持った
のだ。さしずめ、「可愛さ余って憎さ百倍」というところである。
「さあ、しっかり後輩を指導しなさい…」
残酷な笑みを浮かべながら、玉田が美奈をコートに向かわせた。
コートでは、明穂や千花のいる「準レギュラー」グループが、一方がサーブを行いもう一方がレシーブで返
す練習を交互に行っていた。そこに美奈がやって来る。
「乳首を立たせて!」
美奈が大きな声でそう叫び、ギャラリーたちの驚きの声があがる。
「女子テニスでは、オッパイが重要なのよ」
そう言うと、美奈は自ら胸を捲り、指先で乳首を弄りながら指導を始めた。きれいな形の膨らみの頂上で、
ピンク色した小豆大の突起がみるみる勃起してくる。そうして時折、後輩にも胸を露出させ、その乳首を愛撫
して指導した。
「アンスコ食い込ませていくわよ!オ××コに気合を入れて!」
脚を開き、腰を前後に淫らにくねらせながら、美奈の顔は耳まで真っ赤になっている。もちろん自らの意思
で卑猥な掛け声をかけているわけではない。膣と肛門に挿入されたバイブの振動を読み取り、指示されたとお
りの恥ずかしい掛け声を出して、練習を盛り上げているのだ。
その一方で、美奈はできるだけ丁寧に後輩たちの様子を見て、トスのタイミングや上げる位置、コーナーへ
の対処法をアドバイスしていた。しかし、そのためには同時に、必ず不本意で意味のない指導もしなければな
らない。
「明穂、アンスコの食い込みがよく見えないわ」
バイブで送られた指示をもとに、美奈が指導する。
「軽快なフットワークは下半身から。しっかりとオ××コに食い込ませ、体中を性感帯のように感じられれ
ば、自然と体は打球に反応するわ」
「はい!」
美奈の指摘を受けた明穂が、決意を込めた表情で頷いた。コートを出て、観客スタンドの前まで駆けていく
と、スタンドに向けておもいきりお尻を突き出した。スコートの裾が捲れて、白いアンスコに包まれた双臀が
露わになる。薄い生地は割れ目に食い込み、お尻の形がはっきりと映し出されていた。
「明穂のお尻、見てください」
観客に向かってそう言うと、卑猥な腰つきでお尻を振り始めた。プリプリしたお尻に歓声があがる。
観客の一人が調子に乗って近づき、明穂のアンスコに指をかけて引っ張ると、アンスコは一本の紐のように
撚れた。それは彼女の縦裂を割り、ふっくらした肉土手を覗かせる。
「いっ、いや…」
思わずそう叫んで身体をよじり、逃れようとした明穂だったが、「ファイト!」という美奈の掛け声がそれ
を思いとどまらせた。男はニヤニヤ笑いながらアンスコを引っ張って横に寄せ、明穂の秘丘を丸出しにした。
「オッパイの揺れが足りないわよ!」
そう言われた2年生は、頬を染めながらウエアを脱いだ。揺れが足りないというより、乳房が小さいのだ。
やせた胸板に、掌に収まりそうな膨らみがチョコンと乗っているのが見える。それでも指摘されれば、こうし
て上半身裸で練習することで、乳房が揺れる感覚を掴むことが求められるのだ。
「オッパイを揺らすことで、タイミングとバランスを取ることができるわ。オッパイを揺らしながらボールを
打ってもらう、オッパイが小刻みに揺れ、軽快なフットワークでラケットを振るうとボールはコーナーを突
く、オッパイも大きく弾む。ショットの正確さとキレはオッパイの揺らし方で決まるのよ」
後輩の背後に回り、可愛らしい胸の膨らみを撫でながら、美奈はそう言った。
「はい…」
「でも、あなたのオッパイは小さいから、男の人に揉んで大きくしてもらう必要がありそうね」
美奈の言葉を合図に数人の観客がやって来て2年生を取り囲んだ。その双乳が、男たちの手で淫らに形を変
えていく。
「千花、お尻が振れてないわ。レシーブはしっかりとグリップを割れ目に食い込ませ、気持ちを集中させて下
半身の力を抜き、気分を高めるのよ。そうすれば自然と男を誘うように腰が動くわ」
美奈に言われて、千花はもう一方の手を使って、ラケットのグリップを股間に擦りつける。
「ああん…」
千花が小さな喘ぎ声を漏らした。感じ方が足りないとの指摘を受けた者は、こうして、コートに立ったま
ま、絶頂を迎えるまで自らの身体を弄って見せなければならないのだ。
「あっ、ああっ、んんっ…」
千花が軽く目を閉じて、片手でウエアの胸を揉み始めた。もう一方の手に握ったラケットのグリップが激し
く陰部に擦りつけられていた。みるみるうちに、アンスコに恥ずかしい染みができていく。
(ごめんね、みんな…)
美奈の指示で恥ずかしい姿を晒している後輩たちに、彼女は心の中で手を合わせた。しかし、ここで美奈が
手心を加えれば、コーチたちはさらに過酷な練習を指示してくる。
「あんっ、あんっ…、ああっ…」
切ない喘ぎ声とともに、千花の身体がブルブルっと震えてオルガスムスに達した。スタンドの方を見ると、
明穂が興奮した観客たちにバックから犯されている。
逆に、後輩が手を抜けば、指導不足だと美奈に言いがかりをつけ、美奈が厳しいお仕置きを受けることにな
る。心から慕い、慕われる先輩と後輩だからこそ、お互いのことを思いやり、練習とも言えない卑猥な「練
習」をみんなが必死でこなしているのだ。
テニス連盟の常任理事の一人で、観客席の最前列にいた埜田は、美奈の滅茶苦茶な指導に思わず苦笑いし
た。選手からコーチへと進み、今の地位に就いている埜田は、美奈にとっても旧知の顔見知りであった。
「完全に見世物だな…」
嘲笑を含んだ埜田の声が、周りの理事たちの笑い声が、美奈の耳に届いた。彼らが注ぎかける蔑みと憐憫と
好奇の視線が、鋭い矢のように美奈に突き刺さる。
その時、直腸の中でバイブが蠢いた。
「みんな、お尻の穴に力を入れて!」
悔し涙が出そうになるのを堪えて、美奈が大きな声をあげた。
「有岡、次は試合形式で指導してあげなさい!」
玉田の指示を受けて、美奈がコートに立った。
最初の相手は植田陽子だ。星園高校テニス部のキャプテンだった彼女は、スポーツ一本でやってきた恵聖学
園などの部員たちに比べると力不足だと思われていたが、このところ美奈の指導をうけてテニスの実力をつけ
てきた。
最近編入してきた一年生が駆け寄ってきた。まだ幼さが残った可愛らしい顔を真っ赤にして、アンスコを膝
までずらし、少しがに股になった。美奈はその股間に手を当てる。
「うっ…」
一年生が小さく呻いて力む。美奈の手にテニスボールが落とされた。最近、松川が考え出した「ボールガー
ル」という趣向だ。指名された女生徒は、試合開始前に観客の前で脚を開き、陰部を弄られながら、ボールを
膣に挿入されるのだ。
大喜びする観客を前に、少女が悔し涙を浮かべているのが見える。美奈は痛ましさで胸が塞がれそうになり
ながら、一年生の肩に手を置いた。美奈の思いを感じとった彼女は小さく頷くと、けなげな微笑みを浮かべ
た。
陽子がラケットを構えた。男根を象ったグリップは股間の割れ目に当てられ、小刻みに震わせてクリトリス
のあたりを刺激している。あらゆる所作に、卑猥な動きがついてまわるのが、ここでのルールだ。
「いくわよ!」
掛け声をかけて美奈が打ったサーブを、陽子がレシーブして返す。
陽子が打ったボールを、今度は美奈が打ち返す。リターンされたボールは、陽子の練習にとってベストの位
置に返ってくる。そのコントロールは素晴らしいものだった。
美奈は下半身に何も着けていない。コートを駆け抜ける美奈の、大きくひるがえったスコートの下にむっち
りとしたお尻とツルツルの割れ目にこんもりした恥丘の盛り上がり、そして、二本のバイブが突き刺さってい
るのが見える。
陽子が打ったボールは、コートの端近くに飛んだ。余裕で追いついた美奈が、きれいにボースを返し、陽子
の正面に落とす。
(ほほう…、これは…)
埜田は正直、驚きを隠せなかった。前後の敏感な穴に大きな異物を挿入された状態でプレーするのだ、本来
なら、走るどころか、歩くことさえぎごちなくなってしまうだろう。ところが、美奈の動きは全くそれを感じ
させない。
こんな選手を失うのだとしたら、テニス界にとっては大きな損失ではないか、彼の中に眠る良心がそう呟い
た。
「オッパイ、オッパイ!」
卑猥なコールがギャラリー全体に広がる。
悔しさで体が震えるのを我慢し、美奈が胸を突き出したまま乳房を晒し、客席スタンドの前を歩く。囃して
立てる集団がいればバストを寄せ、出来た胸の谷間にラケットのグリップを挟んで先端に舌を這わせ、媚びて
みせた。
カメラを向ける者、露骨に指をさし卑猥な言葉を投げかける者、美奈を真似たポーズを取って侮辱する者、
客の反応は様々だが、皆一様に美奈を見て笑っていた。今や美奈は性欲を煽るための道化なのだ。それを見
て、埜田の中で目覚めかけた良心が、再び淫らな欲望に曇る。
美奈の練習相手は、次々に交替していく。
(あっ…、いけない…)
美奈は慌てて下半身に力を入れた。手を使わなくても、膣口の動きだけでずれ落ちそうになったバイブを呑
み込んでいくのは訓練の賜物だ。
練習中にバイブを落とすことは許されない。しかし、これを支えるものは何もなく、膣口と肛門で締め上げ
て、抜けないように維持しなければならないのだ。膣内が濡れてくると、ぬるぬるの愛液のせいで咥えている
ことがさらに困難になり、何度も落としそうになった。
そうしている間にも、練習は続き、最後の一人の相手を終えた。
「マ×コ、マ×コ!」
猥褻な連呼が湧き起る。美奈は、性奴隷の証ともいえるツルツルに処理された恥丘を客席に示す。二本のバ
イブがニョッキリと生えているのが卑猥だ。
(よし、今だ!)
玉田がリモコンのツマミを思い切り捻った。前後のバイブが強烈な振動を膣口、Gスポット、肛門に与え、
突起がクリトリスを震わせる。美奈は全身に力を入れて、立っていられないほど強力な刺激に耐える。
「うっ…、ううっ!ああぁ!」
美奈がぶるっと身体を震わせた次の瞬間、股間の力が緩んだ。
(しまった…!)
そう思った時は遅かった。女陰から滑り落ちたバイブがコートに転がった。後輩たちの練習を全て終えたと
いう気の緩みもあったのだ。
「なんですか、その有様は!これは、鍛え直す必要がありますねぇ!」
途端に、玉田が大声を上げた。
「今日は、テニス連盟のお歴々がおいでです。直接、指導していただきなさい」
玉田に指示された美奈は、埜田や井筒らテニス連盟の理事たちがいるスタンドに向かう。 その多くが、大
会などのテニスの行事で顔を知っている男たちであった。
一瞬、美奈の表情が険しくなる。彼女が今、もっとも軽蔑すべき男たちが、そこに並んでいた。女にとっ
て、セックスとは他人の身体を体内に受け入れることである。ところが、心の中で嫌悪し、指一本触れられた
くないと思う相手に、美奈は自らセックスをおねだりしなくてはならないのだ。
「オ××コお願いします!」
美奈は練習の時と同じように、キビキビとお辞儀をすると、正面に腰かけていた埜田の肉棒を取り出して、
くるりと後ろを向いた。そして、引き締まったヒップを突き出すようにして、彼の膝の上に腰をおろす。さっ
きまでバイブで苛め抜かれていた女性器は、すぐにでも男を受け入れることができる状態だ。
「うんっ…、あはぁ…」
勃起した埜田の怒張が、美奈の中にじわじわと入っていく。背面座位で繋がった美奈の口から、悩ましげな
声が漏れた。すっかり濡れた粘膜がぬめぬめと肉棒に吸いついて包み込み、挿入しただけでたまらない快美感
を埜田に与えてくれる。
「太くて逞しい、とても立派なオ×ン×ンです…」
卑猥な奉仕をする際、美奈たちはとにかく相手の男性器を褒めるよう命じられている。慰安譲としての立場
を認識させることが目的だ。
「ううっ…」
肉茎を包んだ女膣がぎゅうっと締まり、埜田が小さく呻いた。
「美奈のオ××コの締め具合はいかがですか?」
美奈は腰と脚を使い下半身をひねり、前後に上下に左右にと尻を動かし、膣だけで男に快感を与えていく。
「セックスがテニスのトレーニングに適していたなんて、私ここに来るまで考えてもみませんでした、ここで
トレーニング出来て私たちは幸せです」
「そうかそうか、良かったな」
そう言って笑い合う男たちの表情に、残酷な色が浮かんでいる。まるで、さかりのついた雌犬を見るかのよ
うなその視線に、美奈のプライドはズタズタに切り裂かれていく。それでも、美奈は奉仕を続けなければなら
なかった。それが、玉田の指示であり、そして、彼女自身が秘めている目的にとっても必要なことだ。
「美奈のお口にください。井筒先生のオ×ン×ン…」
「仕方ないなぁ、じゃあ、舐めさせてやろう」
井筒がにやけた顔でチャックを開き、美奈の口元に怒張を差し出す。顔を顰めたくなるような残尿臭が鼻先
をかすめた。
「カリがこんなに張って、すごく硬いです」
そう言いながら、美奈は舌を出して舐めはじめた。柔らかに微笑み、舌腹で裏筋を舐めあげてきた。味わう
ように舐めながら、美奈が上目づかいに井筒を見上げる。視線と視線が絡み合った。
「さすがだなぁ、チ×ポをしゃぶるのが上手いぞ」
「ありがとうございます」
美奈は唾液を怒張全体に塗し、唇に咥え込んでいった。生温かい美奈の口内に、肉茎が呑み込まれていく。
舌先が口内でカリ首に絡んでくる。濡れたヴェルヴェットのような感触を持つ舌だった。
唇奉仕を受けながら、井筒がウエアを捲り上げ、美奈の胸を鷲づかみにして捏ね回す。もう一方の乳房は別
の男が愛撫し、乳首を摘まんでは押しつぶす。その度に美奈の子宮はキュッ、キュッと収縮して、埜田の肉棒
を締め付けた。
「ううっ…」
その収縮感にたまらなくなった埜田が、腰を動かして怒張の抜き差しを始めた。井筒も美奈の頭を押さえ、
口へ挿入する。美奈が頬をへこませて、肉棒を吸い上げる。
「う…むぐぐ…」
井筒が思い切り腰を突き出した。肉棒に喉の奥を突かれ、頬を伝う涙を拭うことも出来ずに咽びながらも、
美奈は必死で舌を動かした。
「舌使い、上手いじゃないか」
井筒が嬉しそうな声をあげて、手加減する様子もなく腰を激しく振る。
その間も幾本もの手が、全身の至るところを撫で回す。誰かの指がお尻の亀裂に沿って這い回り、肛門の中
にまで入ってきた。
「…むっ、むうぅっ!」
くぐもった呻きがひときわ大きくなる。このままでは呼吸困難になりそうに感じた美奈は、井筒のペニスを
口から出して、埜田とのセックスに集中することにした。
「私も…、イキそうです、一緒にイかせて下さい…」
そう言うと、入り口と内部の締め付け絡み具合の違いを生かし、刺激が単調にならないように腰を動かす。
相手にはお尻の弾力が伝わる程度にしか体重をかけない、美奈の足腰だけで腰を上下させ相手を射精させるの
だ。井筒の方も不満を感じさせないように、指先で肉棒をあやしている。
「有岡美奈、イキます!」
「いいぞ、いいぞ。有岡君、最高だ…」
埜田がうれしそうな声を漏らした。耳元で息を吹きかけられ、全身に鳥肌が立つほど嫌悪しながら、美奈は
ひたすら腰を動かし続けた。慰安嬢としてしつけられた身体は、心とは無関係に性感を高めていく。
「イク!」
そう叫んで美奈が絶頂に達した。次の瞬間、彼女の中で熱いものが爆ぜた。襞肉に絡み付くように、男が放
ったぬるぬるの汚濁が膣内を汚していく。
「膣内射精ありがとうございました!」
そう言うと、待たせていた井筒の膝に跨り、ゆっくりと下肢を動かし始めた。
「はぁあっ、はぁぁぁ…」
美奈が喘ぎ声をあげながら、ヒップを前後に揺すり、呑み込んだ肉棒を味わうように柔肉で擦りたてた。
「これはたまらん…」
井筒が満足そうな声を漏らした。ほっそりしたウエストが捻られ、丸みを帯びた尻肉がまるでそれ自体独立
した生き物のように動き、わななく。
「口がヒマしてるぞ。汚れたチ×ポを綺麗にするんだ」
喘ぐ美奈の前に、埜田がぬめぬめした肉棒を突き出した。射精後の臭いが鼻を衝く。
「すみません…」
謝罪の言葉を口にすると、美奈は舌を出して鈴口を舐めた。カリの裏側へと舌を這わせ、男根に付着した精
液と愛液をきれいに舐め取っていった。美奈の甘美な舌を味わった埜田の怒張は、再び大きくなっていく。
井筒が腰を突き上げる。
「ああ…、亀頭がオ××コの壁を擦って気持ち良いです、凄く奥まで感じます」
美奈が喘ぎ声をあげる。同時に、膣の収縮感が格段に増し、井筒の肉棒をきつく締めあげてきた。
「むうぅ…」
井筒はたまらなくなり、ついに美奈の中で果てた。
「………」
美奈が唇をギュッと噛みしめた。こうして男に汚される度に、今でも毎回心の中で泣いている。ここに連れ
て来られた女の子たちは、みんなそうだ。それでも、美奈は、今ではそれを表に出すことは決してなかった。
「まだイケます!もう一発お願いします!」
喘ぎながらそう言った後、美奈は口で、秘孔で男たち怒張をくわえ込み、両手でも怒張をしごかされてい
た。
(そうだ、お前の存在意義はチンポを満足させる事、お前はチンポを突っ込む穴でしかない。
搾り取った精液の量が、今の有岡美奈の価値だ)
凌辱される美奈を見つめる玉田が残酷な笑みを浮かべ、心の中でそう呟いた。
審判台に座った松川は、コートのあちこちで卑猥な練習を繰り広げるテニス少女たちを満足そうな笑いを浮
かべて見渡たしていた。その視線が観客席に向けられた時、松川の表情に緊張が走る。
(えっ、あれは…)
男にしては小柄で、痩せぎすの地味な中年男。それでいて、周囲に暗いエネルギーが渦巻くかのような圧迫
感を感じさせるその姿。見物客の最前列でテニス少女たちの練習を見ているのは、紛れもなく館長、諸藤宗光
だ。
駆け寄って声をかけようとした松川の動きが止まる。普段は表情が読み取りにくい諸藤の顔に浮かんでいる
のは、明らかに不満の色であった。さすがの松川も、凍りついたように動けなくなってしまった。
それでも勇気を奮い立たせ、声をかけようと審判台から降りた松川だったが、その時既に、諸藤の姿は観客
席から消えていた。
新宮の計画を具体化するためには、諸藤の了解をとりつける必要がある。最初に理事選挙について声をかけ
た時に、諸藤は協力を約束してくれていた。しかし、…。
今見た諸藤の表情に、松川の不安が高まる。不満の理由を彼が口にすることはないだろう。先に気づいて手
を打たないと、切られるのは自分だ。
「これは、館の幹部の中で、誰か味方が必要だな…」
松川はそう呟いて、真剣に策を巡らせた。
|
|